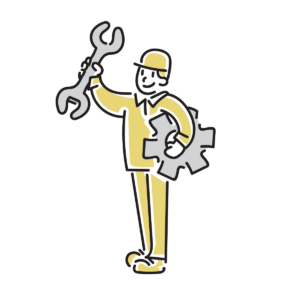所得税・相続税・贈与税…“生計を一にする”がカギとなる税務の実際
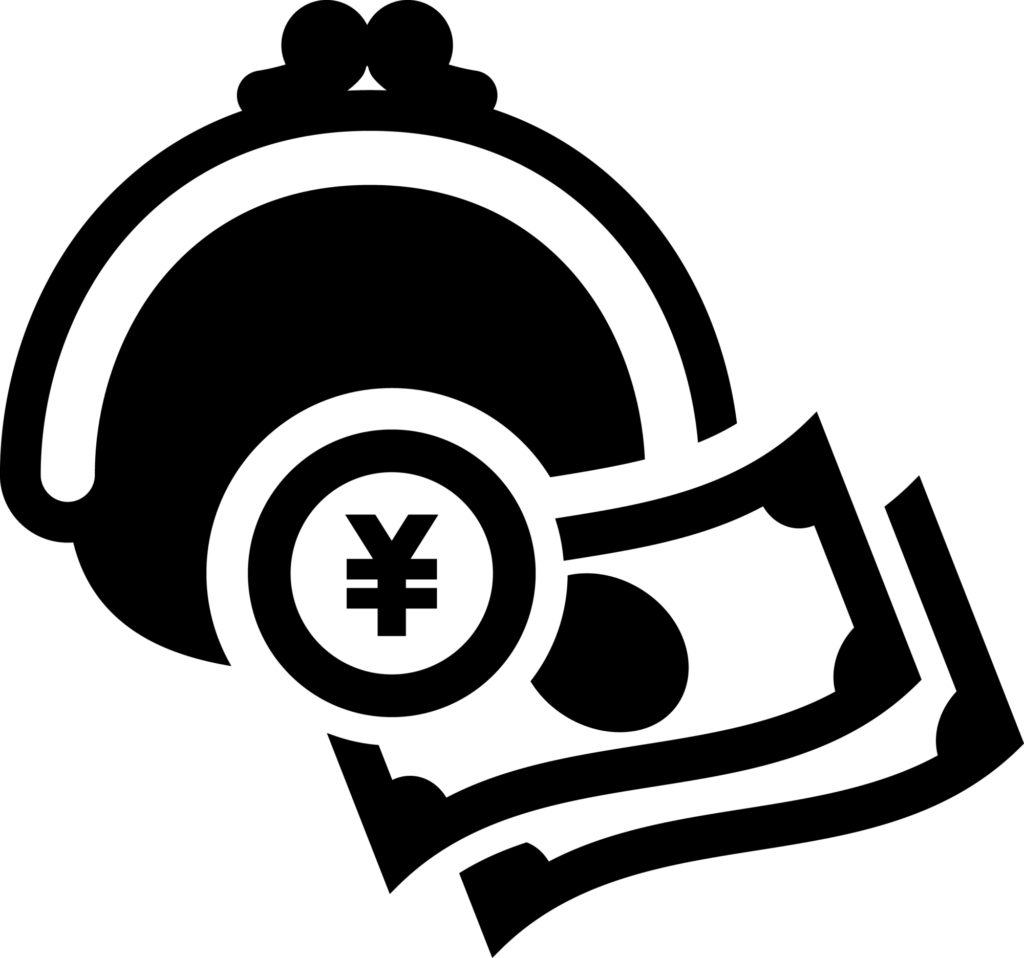
税務実務において、「生計を一(いつ)にする」かどうかは、所得税・相続税・贈与税など複数の税目で重要な判断基準となります。
「生計を一にする」の認定は、人的控除や特例適用、非課税の範囲など、納税者の税負担に大きな影響を及ぼします。
しかし、単なる同居・別居の有無だけでなく、生活費のやりとりや家計の実態など、実務上は判断が難しいケースも少なくありません。
今回は、「生計を一にする」が税務処理に与える影響とその論点を、具体的に解説します。
目次
生計が一とは
「生計を一にする」とは、同居・別居を問わず、家族や親族が日常生活の資金を共通にして生活している状態を指しますが、同居の場合は基本的に生計を一にしているとみられます。
たとえば、生活費や学費、療養費などを一方が負担し、もう一方がその資金で生活している場合や、別居していても定期的に生活費の送金があれば「生計を一にする」と認められます。
逆に、同居していても家計が完全に独立していれば該当しません。
税法上の控除や特例の適用判断で重要な基準となります。
生計が一かどうかの分かれ目
「生計が一かどうか」の判断は、単なる同居・別居の有無ではなく、家計や生活費の実態に基づいて総合的に行われます。
分かれ目となる最大のポイントは、「生活の資を共通にしているか」、すなわち“同じ財布”で暮らしているかどうかです。
たとえば、進学のために一人暮らしをしている子どもが親から定期的に仕送りを受け、家賃や学費、生活費を親が負担している場合、別居でも「生計を一にする」と判断されます。
一方で、成人した子どもが就職し、自分の収入だけで生活している場合は、たとえ同居していても家計が完全に独立していれば「生計を一にする」とは認められません。
また、両親が年金などで自立して生活できている場合、子どもからの仕送りがなければ「生計を一にする」関係には該当しません。
逆に、別居している高齢の親族に対して生活費を負担している場合は、「生計を一にする」とみなされることがあります。
判断基準としては、収入や生活費の負担状況、水道光熱費や家賃の支払い、住民票や社会保険の世帯状況などが挙げられます。
たとえば、二世帯住宅で居住スペースも家計も完全に分かれていれば同居でも「生計を別にする」とされやすく、逆に別居でも生活費の送金があれば「生計を一にする」と認められる場合があります。
生計が一かどうかで取り扱いが変わるもの
所得税:配偶者控除・扶養控除等の人的控除
所得税の人的控除(配偶者控除・扶養控除・ひとり親控除など)は、納税者と控除対象者が「生計を一にする」ことが基本要件となっています。
たとえば、配偶者控除を受けるためには、納税者と配偶者が生計を一にしている必要があり、単に婚姻関係があるだけでは認められません。
同様に、扶養控除も「生計を一にする」親族でなければ対象外です。
ここでの「生計を一にする」とは、生活費や学費などの資金を共通にしている状態を指し、必ずしも同居している必要はありませんので仕送りを受けている学生や単身赴任をしている家族なども認められるケースがあります。
配偶者控除や扶養控除の対象になる方はそもそも年間の所得金額が58万円以下の方となります。
他に資産が無ければ自身の収入だけで生活を成り立たせるのが難しいケースが多く家族の支援を受けていることも考えられますので、多くの場合で生活資金は共通していることでしょう。
また扶養親族が国外に居住している場合などに必要になってくる生計を一にすることを明らかにする書類(送金関係書類)も年末調整や確定申告では必要になってきますので予め準備が必要です。
所得税:医療費控除・雑損控除の範囲
医療費控除や雑損控除も、「生計を一にする」親族が対象となります。
医療費控除では、納税者自身だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費も控除の対象です。
たとえば、遠方に住む子どもに仕送りをしている場合、その子どもの医療費も控除対象となることがあります。
雑損控除も同様で、生計を一にする親族が所有する生活用資産の損失が控除対象です。
災害や盗難による損失が発生した場合、家計の実態が問われることになります。
このほか社会保険料控除や地震保険料控除なども同様に生計を一にする親族に係る支払が控除対象となります。
控除を適用する際は、生活費の送金記録や資産の所有関係を明確にしておくことが大切です。
所得税:事業所得における専従者給与・控除
個人事業主が「生計を一にする」親族に対して支払う給与や家賃、利子などは、原則として必要経費に算入できません。
ただし、青色申告者の場合は「青色事業専従者給与」、白色申告者の場合は「事業専従者控除」として、一定の要件を満たせば必要経費とすることができます。
ここでも「生計を一にする」ことが要件となっており、たとえば親族が別居していても、生活費のやり取りや家計の共通性があれば認められる場合があります。
逆に、家計が完全に独立している場合は通常の給与と同様の取り扱いとなります。
所得税:住宅ローン控除の上乗せ措置
住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、一定期間にわたり年末時点の住宅ローン残高に応じて所得税から控除を受けられる制度です。
近年の税制改正により、子育て世帯や若者夫婦世帯など特定の条件を満たす場合、住宅ローン控除における「借入限度額」が通常よりも上乗せされる特例措置が設けられています。
19歳未満の子供を扶養している場合に上乗せ措置の適用を受けられますが、この子供とは生計を一にしていることが要件の一つとなっています。
法人税:同族関係者の範囲
同族会社の判定や特定の取引における関係者の範囲を定める際に、生計を一にする親族が含まれるかどうかが重要になってきます。
生計を一にする同族関係者と判定されることで、特殊関係使用人の範囲が変わったり、同族会社へ該当したりと影響が出てきます。
相続税:小規模宅地等の特例
相続税における「小規模宅地等の特例」では、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が事業や居住の用に供していた宅地について、相続税評価額を大幅に減額できる特例があります。
この小規模宅地の特例は事業や生活の維持のために欠くことのできないものであるためその処分に一定の制約があり、相続財産の担税力が減少しているため相続税の負担を軽減するために設けられた特例です。
この「生計を一にする」かどうかの判定は、同居の有無や生活費や家計の共通性、被相続人の日常生活の支援の有無など実態に基づいて総合的に判断されます。
同居していても光熱費を別々に支払っていたり、家賃のやり取りがあるなど家計が別であれば認められない場合があり、逆に別居でも生活費の送金や定期的な同居があれば認められることもあります。
特例適用の有無は納税額に大きな差を生むため、家計の実態や資金の流れを証明する資料の準備が不可欠です。
税務調査では、生活費のやり取りや居住実態が厳しく確認されるため、事前の証拠保全が重要となります。
贈与税:生活費・教育費の非課税規定
贈与税では、扶養義務者が「生計を一にする」親族に対して、生活費や教育費として必要な都度、直接充てるために贈与した財産については非課税とされています。
非課税となるためには、贈与の都度必要な分を直接支出することが要件であり、多額の一括贈与や使途が不明確な場合は課税対象となる可能性があります。
たとえば、子どもの学費や日常の生活費を親が送金する場合、使途や金額が明確であれば非課税となりますが、預貯金として残った場合や他の用途に使われた場合は課税されることがあります。
実務上は、送金記録や使途を明確にすることが重要です。
まとめ
「生計を一にする」かどうかは、所得税・相続税・贈与税など多くの税目で税務処理に大きな影響を与えます。
単なる同居・別居だけでなく、生活費のやり取りや家計の実態など、実際の生活状況に基づいて判断されるため、証拠書類の整備や資金の流れの明確化が不可欠です。
筒井会計事務所では書類の準備や特例の適用可否など、事前のご相談から承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。