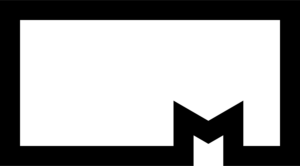小さな会社でも油断禁物!経理の不正を未然に防ぐ会社の仕組みづくり

「ウチの会社に限って、不正なんて起きないよ」そう思っていませんか?
残念ながら、経理の不正は会社の規模に関わらず、どこでも起こりうるのが現実です。
今回は、経理不正が起きる仕組みとその対策をちょっとだけ踏み込んだ目線で解説します。
気づかないうちに、会社の財産が蝕まれているのを防ぐために、ぜひ一緒に考えていきましょう。
目次
不正はなぜ起きる?「機会・動機・正当化」のトライアングル
「不正はなぜ起きるのか?」これを理解することは、対策を立てる上で非常に重要です。
心理学の研究では、不正は「機会」「動機」「正当化」という3つの要素が揃った時に発生しやすいと言われています。
いわゆる「不正のトライアングル」です。
まず「機会」とは、不正ができる状況やスキがあることです。
例えば、経理担当者一人に全てを任せきりにしていたり、チェック体制が甘かったりする場合がこれに当たります。
次に「動機」は、不正をする人の個人的な事情です。
借金返済に困っている、贅沢な暮らしがしたい、といった個人的な金銭的欲求が背景にあることが多いです。
そして「正当化」とは、不正をする人が「これだけ大変な仕事をしているのだから、これくらいの利益を得るのは当然だ」「会社は私がいなければ成り立たないのだから、少しぐらい融通を利かせても良いだろう」などと、自分の行為を都合よく解釈してしまうことです。
これらの要素が一つでも欠ければ不正は起こりにくいとされています。
つまり、会社としてはこの「機会」を徹底的に排除することが重要になってきます。
こんな手口に要注意!巧妙化する不正の事例
「実際にどんな手口があるの?」そう思われた方もいるかもしれません。
残念ながら、不正の手口は日々巧妙化しています。
代表的な事例を見ていきましょう。
例えば、経理責任者による預金からの不正出金は典型例です。
オンライン決済を悪用して自分名義の銀行口座へ資金を送金したり、上司の印鑑を不正に利用して払戻請求書を作成し、現金を引き出すケースもあります。
また、直接的な現金の着服だけでなく、商品在庫の横領もよくあるケースです。
会社の備品や販売用の商品を無断で持ち出し、自身の家事用として消費したり、フリマアプリやオークションサイトなどで転売して個人的な利益を得る、という手口が挙げられます。
これは、在庫管理や棚卸が厳密に行われていない場合に発生しやすい不正です。
さらに、経理担当者が個人の家事費(掃除機、洗濯機、食費など)を会社の経費として精算するといったケースも実際にあります。
これは、領収書やレシートの支払内容のチェック体制が不十分な場合に発生します。
これらの不正は、会計帳簿に全く記帳しない、架空の買掛金支払いを偽装する、棚卸報告書の在庫数量を改ざんする、オンラインバンキングの入出金記録を破棄・偽造するといった数々の偽装・隠蔽工作とセットで行われるため、発見が非常に難しいのが実情です。
対策
これらの不正に対して会社がとれる対応策としては下記のようなものが挙げられます。
「職務分掌」で役割を分ける
経理の不正を防ぐ上で、まず取り組んでいただきたいのが「職務分掌(しょくむぶんしょう)」の徹底です。
職務分掌とは、簡単に言えば「一人にすべてを任せない」ということ。
例えば、現金の出し入れや実際の振込、会計ソフトへの入力、そして銀行との照合まで、これらをすべて同じ人が行うのは非常に危険ですし、もし不正をしようと思えば、簡単にできてしまう「機会」を与えてしまうことになります。
月次決算で月末の残高を合わせることも必要なくなり、誰にも指摘されることもないので資金日報を作成しなくなっていた、といった状況は不正を招きやすくなります。
現金の管理をする人、伝票を作成・承認する人、そして帳簿に入力する人、といった具合に、複数の人で役割を分担することが理想です。
特に、実際にお金を扱う業務と、それを記録する業務は、必ず別の人が担当するようにしましょう。
小さな会社で人員が限られている場合でも、例えば社長が銀行の通帳を定期的に確認したり、支払いの基となる請求書などの証憑をすぐに確認できる体制を整える、といった形で、必ず「複数人の目」を通す仕組みを作ることが重要です。
ちょっと手間だと感じるかもしれませんが、これが会社の財産を守るための最も基本的で強力な盾になります。
預金・現金の定期的な確認
会社の財産であるお金が「いつ」「どこへ」「いくら」動いたのか、これを常に「見える化」しておくことが不正防止には不可欠です。
具体的な方法としては、預金口座と現金残高の「定期的な確認」を徹底しましょう。
預金については、通帳やインターネットバンキングの取引履歴を毎月、少なくとも週に一度はチェックする習慣をつけるのがおすすめです。
特に、いつもとは違う相手への送金や、覚えのない入出金がないか、金額が大きすぎないか、といった点に注意して見てみましょう。
会計ソフトと銀行口座を連携させている場合でも、自動取り込みだからと安心せず、必ず実際の明細と帳簿の記録が一致しているか突合することが大切です。
現金についても、小口現金などがある場合は、毎日あるいは毎週決まった曜日に必ず残高を数え、帳簿と合っているか確認しましょう。
もし頻繁にズレが生じるようであれば、管理方法を見直すサインかもしれません。
お金の動きを常にクリアにしておくことで、もしもの時にも異変にいち早く気づけるようになります。
税理士などとの連携を強化
ここまで、社内でできる不正防止策についてお話ししてきましたが、どんなに完璧な仕組みを構築しても、人間が行うことに「絶対」はありません。
そして、経理の不正は巧妙に隠蔽されることも多く、自社だけで全てを見抜くのは非常に困難です。
そこで有効になるのが、私たち税理士や公認会計士のような「外部の専門家」の存在です。
ただし、ここで誤解していただきたくないのは、税理士が不正を「必ず」見つけられるわけではないということです。
私たちの役割はあくまで、税務申告を適正に行うために帳簿や証拠書類をチェックすることであり、不正を見つけることを主たる目的とはしていません。
しかし、第三者の冷静な目で帳簿や経理処理をチェックすることは、不正発見やその抑止に効果が期待できる強力な「いちツール」となります。
自社だけのチェックでは見落とされがちな不自然な点や、巧妙に隠された不正の兆候を発見する可能性が高まります。
第三者がチェックしているという事実は不正を行う者の動機を抑える効果もあります。
「税理士に任せているから安心」と丸投げするのではなく、積極的にコミュニケーションを取り、会社の現状を共有することで、自社だけのチェックでは不足している効果を補い、より強固な不正防止体制を築くことができます。
万が一の事態に備え、専門家を「会社の番人」として活用する視点もぜひ持っていただければと思います。
まとめ
経理の不正は、どんな会社でも起こりえますので決して他人事ではありません。
しかし、過度に恐れる必要はなく、今回お伝えした対策を一つずつ実行することで、不正が起きる「機会」を大幅に減らすことができます。
会社の財産を守り、健全な経営を続けるためにも、ぜひ今日からできることから取り組んでみてください。
不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。