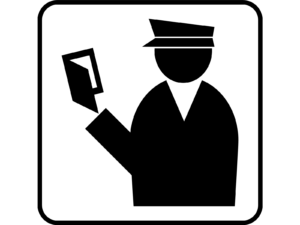青色事業専従者給与、その金額設定は大丈夫?

家族への給与支払いで節税を図る「青色事業専従者給与」制度、きちんと活用できていますか?
この制度は上手に使えば大きな節税効果をもたらしますが、税務調査での否認リスクが高い項目でもあります。
特に給与額の設定は慎重に行う必要があり、「労務の対価として相当」かどうかが厳しくチェックされ、給与額の変更時にもその妥当性が問われるケースが増えています。
令和7年度の税制改正を機に給与額の見直しを検討している方も多いのではないでしょうか。
今回はその際の注意点を踏まえ、実務で役立つポイントを分かりやすく解説します。
目次
青色事業専従者給与制度の基本要件と届出における注意点
青色事業専従者給与制度は、個人事業主が生計を一にする家族に支払う給与を必要経費として計上できる青色申告の特典です。
この制度を利用するには複数の要件をクリアする必要があります。
- 納税者本人が青色申告の承認を受けている
- 青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署長に提出している
- 専従者となる家族が年間6か月を超えて事業に専ら従事している
- 専従者となる家族が15歳以上
実務上特に注意すべきは届出の提出タイミングと内容です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」は、原則として給与を支払う年の3月15日まで(新規開業の場合は開業から2か月以内)に税務署へ提出しなければならず、支給額を変更する場合も変更届出書を提出する必要があります。
また、必要経費と認められるかどうかの判断は、変更届出書の記載額に限らず、過去に提出済みの届出書に記載した額も含めて総合的に判断されます。
また、専従者給与を受け取る家族は配偶者控除や扶養控除の対象外になります。
給与額によっては控除を受けた方が有利な場合もあるため、事前にしっかりとシミュレーションを行い、どちらが得策かを検討することが重要です。
税務調査で否認されやすいパターン
事業に専ら専従しているかどうか
まず、「専従性の欠如」は、青色事業専従者の最も基本的な要件である「年間6か月超、専ら事業に従事」を満たしていないケースです。
この年間6か月超というのは通常の場合で、新規開業時など事業を行った期間が1年に満たない場合は、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間かどうかで判定されます。
例えば、届出はしているものの実際には他社に勤務している、学生で学業と両立している、育児や介護が主で事業への関与が週に数時間程度しかない、といった実態がある場合には否認リスクが高まるでしょう。
対策としては、具体的な業務分担表の作成や、専従者の勤務時間を管理している出勤簿などの備え付けが効果的です。
給与の金額は実際の労働内容に見合っているか
週2〜3日程度の勤務で月額30万円といったケースでは、時給換算すると一般的な水準を大きく上回り、否認される可能性が高くなります。
他の従業員と同等の、あるいはより高い給与を支払う場合は、その金額に見合うだけの専門的な技術や知識、責任の重さなどが必要です。
対策としては、業務日報の作成などにより専従者の仕事内容を明らかにし、給与の金額の決定根拠として疎明できる状態にしておくことが有効です。
事業的規模かどうか
青色事業専従者給与制度は事業を行っている納税者が適用できる特典になりますので、事業といえない規模の業務では青色事業専従者給与を支払うことはできません。
主たる勤務先がある中で副業や、一般的に事業的規模といえない不動産投資から事業専従者給与を支払っていたりする場合も税務調査で否認される可能性は高いでしょう。
税務調査では、そもそも事業として成り立っているのか、単なる趣味や副業レベルではないかという点が厳しくチェックされ、事業性が否定されると専従者給与も一括否認される危険性があります。
事業的規模の判定で重要なのは、継続性と営利性、そして規模の妥当性です。
継続性については、一時的な活動ではなく反復継続して行われているかがポイントとなります。
例えば年に数回しか取引がない場合や、開業届は出したものの実際にはほとんど営業していない状況では事業性を疑われます。
営利性の判断では、利益を得る目的で行われているかが問われます。
毎年赤字が続いている事業で高額な専従者給与を支払っていると「所得分散が目的では?」と疑念を持たれがちです。
規模の妥当性では、売上高、取引先数、従業員数などが総合的に評価されます。
年商100万円程度の小規模事業で専従者給与年額300万円では明らかにバランスを欠いています。
給与額は急激に変動していないか
給与額の急激な変動も疑念を持たれがちです。
給与改定には合理的な理由(業務拡大、資格取得、責任増加、給与相場の変動など)を用意し、書面で記録しておくことが重要です。
令和7年度の税制改正により、所得税の基礎控除額等が引き上げられ、年間給与収入160万円までは所得税が課されなくなったことを受け、給与の改定を検討している場合は注意が必要でしょう。
給与額の見直しを行う際には、賃上げの理由(事業の業績向上、物価上昇への対応など)を明確にし、他の従業員の給与改定と合わせて行うなど、合理的な根拠を準備しておくことが不可欠です。
いずれのパターンにおいても重要なのは、主観的な主張ではなく、客観的な資料で専従性や給与の妥当性を証明できるかという点です。
「労務の対価として相当」な金額の判断基準
専従者給与で最も重要かつ判断が難しいのが、支払う給与額が「労務の対価として相当」かどうかの判定です。
税法上は明確な金額基準が示されていないため、実務では様々な要素を総合的に勘案して判断する必要があります。
税務署が否認の際に用いる代表的な手法が「類似同業者給与比準方式」です。
これは、業種や事業規模が類似する他の事業主が、親族に支払っている給与の平均額を算出して妥当性を判断するものです。
さらに事業規模との整合性も見られます。
年商1,000万円の事業で月額50万円の専従者給与では、事業規模に対して過大と判断される可能性があります。
売上に対する給与の割合や、事業主本人の所得との比較も重要な判断要素となります。
親族ではない他人であっても同様の金額を支払えるかどうかが妥当な金額のラインと言えるでしょう。
まとめ
青色事業専従者給与制度は、適切に活用すれば大きな節税効果をもたらす特例です。
しかし、給与額の設定や変更時には、労務の対価として相当かどうかなど、複数の検討すべき論点があります。
令和7年度の税制改正を機に給与額を見直す際も、単なる節税目的ではなく、客観的な根拠(業務内容の変更、他の従業員の賃上げ状況など)を用意しておくことが不可欠です。