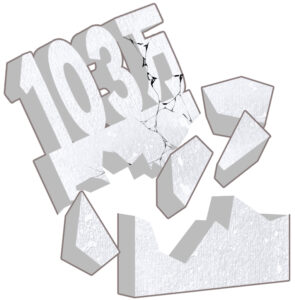相続時精算課税とは?賢く使うための基礎知識と注意点
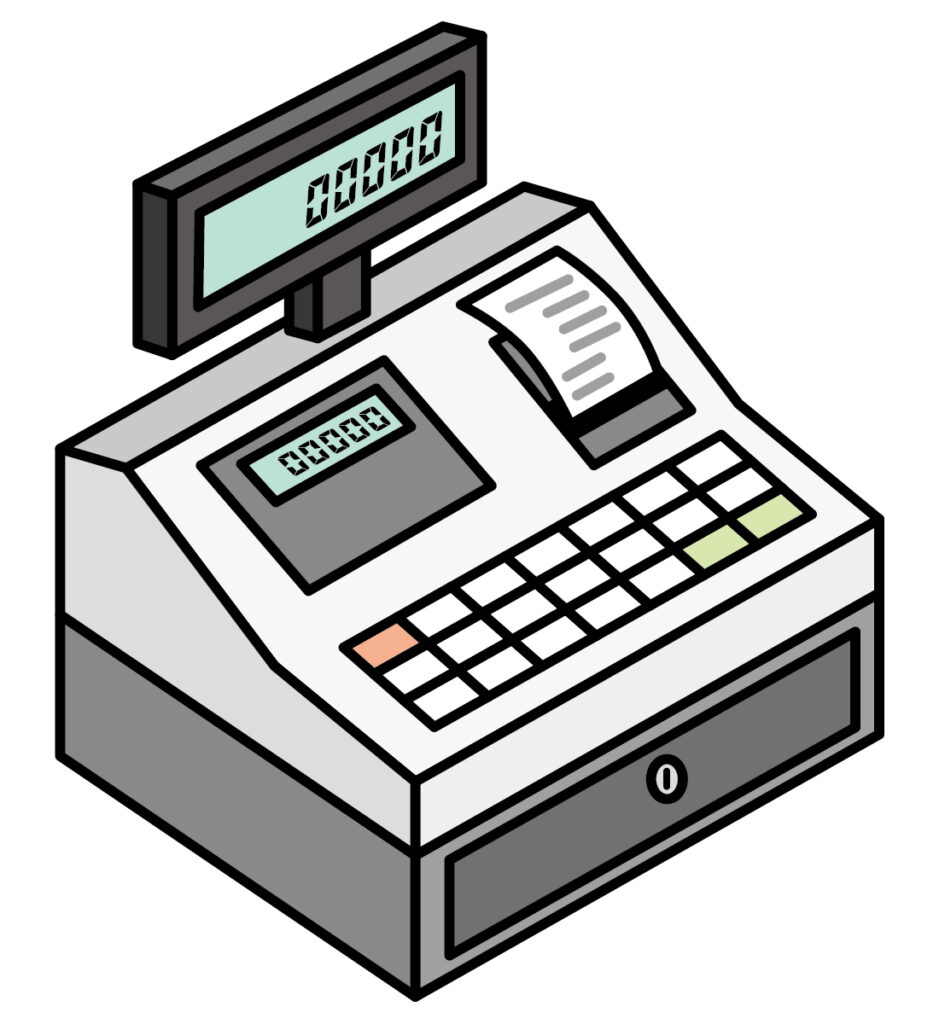
令和6年の改正により、相続対策の手段として注目される「相続時精算課税制度」。
この制度は、贈与を受けた段階で贈与税を一部納め、将来の相続時に最終的な税額を精算する仕組みです。
今回はこの制度の基本と、制度選択の際に押さえておきたい実務上のポイントを分かりやすく解説します。
制度の全体像を理解し、失敗のない相続・贈与対策に役立てましょう。
目次
相続時精算課税の概要と仕組み
相続時精算課税制度とは、原則として親や祖父母からの贈与に対し、2,500万円までの特別控除を適用しつつ、一律20%の贈与税率で課税し、将来の相続時にその贈与分を精算して相続税を再計算する仕組みです。
贈与を受けた段階では、相続税の前払いのような位置づけで贈与税を計算・納付し、相続が発生した際に再度、贈与分を含めて相続税を計算します。
そして、贈与時に納めた贈与税分を差し引いて精算します。
この制度の大きな特徴は、贈与時にまとまった資産を移転できる点です。
たとえば、不動産など評価額が将来的に上昇しそうな資産を早めに移すことで、節税効果が期待できます。
ただし、一度この制度を選択すると同一の贈与者については暦年課税方式に戻すことはできません。
適用要件と手続きの流れ
贈与時
制度を利用するためには、受贈者が贈与者の「推定相続人」もしくは「孫」であり、贈与年の1月1日時点で18歳以上であることが必要です。
また、贈与者は原則として贈与年の1月1日時点で60歳以上である直系尊属(例:父母・祖父母)である必要があります。
初めてこの制度を利用する際には、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書とともに提出する必要があります。
申告書には「申告書第一表」「第二表」および必要な添付書類を含めて税務署に提出します。
また、複数年にわたり贈与を受ける場合、特別控除額は累計で2,500万円までとなり、超過分には20%の贈与税が課されます。
相続発生時
相続時精算課税制度を適用して贈与した財産を本来の相続財産に加算して相続税を計算します。
この時に加算する金額は、相続時の時価ではなく贈与時の価額となります。
また二重課税を排除するために、相続時精算課税制度に係る贈与税を相続税から控除します。
この時、贈与税額>相続税額だった場合は贈与税額の還付を受けることができます。
(暦年課税の生前贈与加算の場合は、贈与税の還付を受けることはできません。)
特別控除額・基礎控除額の考え方と計算例
相続時精算課税では、特定の贈与者から贈与を受けた際、まず110万円の基礎控除額があり、これを超える部分に対して特別控除額2,500万円を限度として差し引くことができます。
例えば、令和6年に父から1,610万円、令和7年に1,910万円の贈与を受けた場合、総額は3,520万円になります。
このうちそれぞれ基礎控除110万円を控除した残額から特別控除額2,500万円を適用した後の800万円が課税対象となり、これに20%を乗じて160万円の贈与税が発生します。
| 贈与財産 | 基礎控除 | 特別控除額 | 課税価格 | 贈与税額 | |
| 令和6年 | 1610万円 | 110万円 | 1500万円 | 0円 | 0円 |
| 令和7年 | 1910万円 | 110万円 | 1000万円 | 800万円 | 160万円 |
また、この課税済の贈与財産は、将来の相続時に相続財産として加算され、改めて相続税額が計算されます。
このケースの場合、相続財産に加算される金額は令和6年分の1500万円と令和7年分の1800万円の合計3300万円となります。
その際、すでに納付した贈与税160万円は相続税から控除されるため、二重課税にはなりません。
制度選択のメリット・デメリット
【メリット】
- 一度に多額の資産を移転できる(最大2,500万円まで非課税)
- 将来値上がりが予想される資産を早期に移転し、節税効果が期待できる
- 贈与を計画的に行えば、相続税対策や相続争い対策になる
- 基礎控除110万円が利用できる
【デメリット】
- 一度選択すると暦年課税に戻れない
- 相続時精算課税選択届出書の提出や相続税申告時に忘れずに加算しなければならないなど手間が多い
- 小規模宅地を適用できる不動産を贈与してしまうとトータルの租税負担が大きくなる
- 不動産を贈与する場合の登録免許税や不動産取得税などの流通税が相続の場合より大きくなる
- 将来の制度改正などにより思わぬ不利益が生じる可能性がある
制度の選択は、贈与者・受贈者の年齢や資産内容、将来のライフプランを総合的に考慮する必要があります。
安易な選択はかえって税負担を増やす結果になりかねません。
相続での取得ではダメなのか、贈与するにしても暦年課税制度との有利不利の検討を行いましょう。
また相続時精算課税制度を受贈者の方が選択すると他の推定相続人の相続税にも影響が出ますので家族のコンセンサスを事前にとっておくことが大事です。
注意点
贈与税の申告が期限後になる場合
相続時精算課税制度を適用して贈与税を申告する場合に、その申告が期限に間に合わなかったときは特別控除額2500万円は適用されません。
基礎控除110万円は控除されますのでその残額に対して20%の贈与税が課税されます。
ただし相続時精算課税選択届出書は期限内に適法に提出されている場合に限りますので注意が必要です。
受贈者が贈与者より先に亡くなった場合
財産を贈与により取得した受贈者が、財産の贈与者より先に亡くなった場合は、受贈者の相続人が法定相続割合で承継することになっています。
受贈者の相続人の中に贈与者が入っていたときはその贈与者がいないものとして法定相続割合を計算することとされております。
受贈者の相続人が贈与者より先に亡くなった場合も同様にさらにその相続人に承継されていきます。
これらの相続人が贈与者のみとなった場合には、その相続時精算課税制度に係る権利義務は承継されないこととなります。
人がいつ亡くなるかは予測できませんが、様々なパターンを想定しておくことが想定外の税負担を生じさせない予防策になります。
基礎控除は特定贈与者ごとに按分
令和6年以降、相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が新設されましたが、同一年に複数の贈与者からこの制度を適用して贈与を受けた場合は、それぞれの贈与額に応じて按分されます。
控除計算が複雑になるため、実務では細かな確認が欠かせません。
贈与を受けた不動産が罹災した場合
親から土地や建物を贈与されて、それを持ち続けていた場合に、その後に災害で壊れてしまった場合、その不動産の価値が下がります。
今までは贈与されたときの高い価値で相続税が計算されていましたが、令和6年1月1日以降被災した場合は、被災によって下がった分を差し引いて実際の価値で計算できるようになりました。
これにより、災害で損をしても、税金の負担を少なくすることができます。
ただし、災害発生日から3年を経過する日までに罹災証明書などを添付して一定の申請書を税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。
まとめ
相続時精算課税制度は、相続税対策として有効な手段である一方で、選択の仕方を誤ると予想外の税負担が発生するリスクもあります。
制度の仕組みや控除の内容、適用要件を正しく理解し、贈与者・受贈者・推定相続人の将来を見据えた戦略が重要です。