土地と建物を一緒に買ったら取得費はどうなる?取得費の考え方と注意点
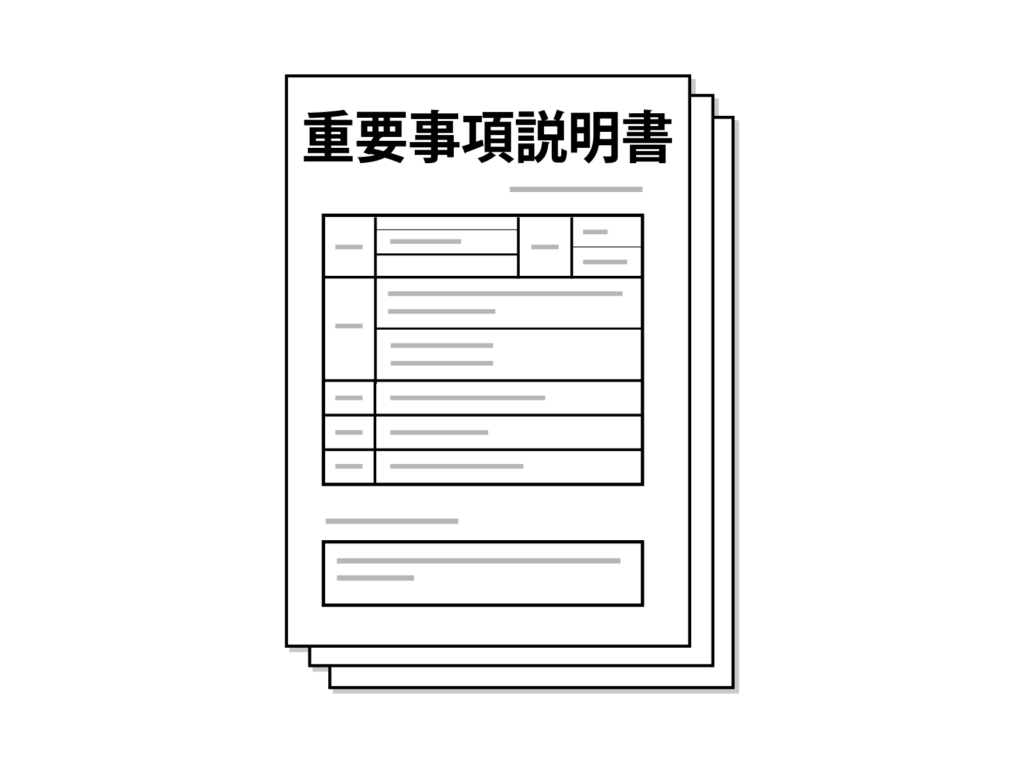
不動産を売却したときに計算される「譲渡所得」。
譲渡所得は基本的に売却金額-(取得費+譲渡費用)とされるため「取得費」がいくらとなるかで税額にも多く影響します。
取得費とは、買ったときにかかったお金や、売るまでに加えた価値(リフォーム費など)を合計したものとなります。
ただし、土地と建物を一括で購入している場合や、領収書が残っていない場合は計算がひと工夫必要です。
今回は、取得費の基本から応用まで、分かりやすくご紹介します。
目次
取得費とは何か
取得費とは、不動産を購入する際にかかった総費用を指します。
具体的には、土地や建物の購入代金に加え、不動産に追加した設備の費用や改良した費用も取得費となります。
また以下のような支払も取得費に含まれることになります。
- 購入時にかかった税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税など)
- 借主がいる場合に支払った立退料
- 仲介手数料
- 測量費
- 整地費や建物の取り壊し費用
減価償却の考慮
建物を売却した場合の取得費は購入代金から減価償却費を差し引いた額になります。
これは、建物が時間とともに価値を減少させるため売却価格も逓減していくのに対応させるためです。
この減価償却費は事業用か、それ以外かによって計算方法が異なるので注意が必要です。
事業用(または不動産貸付用)
事業所得や不動産所得を計算する際に減価償却費を毎年計上しますので、その累計額を控除します。
つまり取得費は購入価格-減価償却費累計額となり、売却時点の帳簿価格となります。
事業用以外(居住用など)
実際の経費計上はしませんが、譲渡所得計算上は旧定額法で計算となり、事業用の1.5倍の耐用年数を用います。
| 区分 | 木造 | 木骨モルタル | (鉄骨)鉄筋コンクリート | 金属造り① (軽量鉄骨の骨格材の肉厚3㎜以下) | 金属造り② (軽量鉄骨の骨格材の肉厚3㎜超4㎜以下) |
| 耐用年数 | 33 | 30 | 70 | 28 | 40 |
| 償却率 | 0.031 | 0.034 | 0.015 | 0.036 | 0.025 |
償却費の具体的な計算式は以下の通りとなります。
償却費(取得価額の95%限度)=取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数
経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
土地と建物を一括購入した場合の取得費の分け方
上記のように不動産を売却した際の取得費を計算するには、その建物の取得費がわからなければ償却費の金額がわかりません。
しかし、売買契約書で土地と建物の価額が区分されていない場合や、そもそも契約書を紛失してしまった場合、取得費の計算が難しくなることがあります。
契約書で建物の取得費がわかるケース
土地建物を一括で購入しても、売買契約書に土地・建物それぞれの金額が記載されている場合は基本的に記載されている金額で区分します。
また、土地・建物それぞれの金額が記載されていなくとも、消費税の金額が明記されている場合(『うち、消費税●●円』などと記載がある場合)では、その消費税の額を、その売買契約時の消費税率で割り返すと建物の金額を計算することができます。
これは土地の購入には消費税が課されず、建物の購入にのみ消費税が課されるためです。
これらの方法により計算された土地と建物の金額が、当時の土地と建物の時価からみて不合理に乖離していなければこの区分方法を適用することができます。
契約書で建物の取得費が判明できないケース
売買契約書において土地と建物の価額が区分されていない場合、以下のような方法を用いて、合計額を土地と建物とに按分して区分する必要があります。
時価による按分
土地や建物の時価がわかる場合にはそれぞれの金額で按分して計算します。
時価の算出方法にもよりますが、恣意性が入りやすいため第三者による時価の算出が望ましいです。
固定資産税評価額による按分
土地と建物の売却した年の固定資産税評価額をもとに按分する方法です。
実務上は最も採用されやすい方法で、固定資産税の通知書等があれば比較的容易に按分が可能となります。
建物の標準的な建築価額表による按分
建物の標準的な建築価額表をもとに建物の取得価額を算出し、差額を土地の価額とする方法です。
国税庁の「譲渡所得の申告のしかた」でも、この方法を用いることに差し支えないとされています。
建物の標準的な建築価額表を用いる場合、新築と中古で建物の取得費の計算方法が異なります。
- 新築の建物を購入した場合
- 計算式: 「建物の標準的な建築価額表」の建築単価 × 建物の床面積 = 建物の取得価額
- 中古の建物を購入した場合
- 計算式: (「建物の標準的な建築価額表」の建築単価 × 建物の床面積) – 償却費相当額 = 建物の取得価額
- ここでいう償却費相当額とは、建築から取得までの経過年数に応じた額を指します。
この他にも相続税評価額による按分などいくつかの方法が考えられますが、ご自身のケースに合った方法で合理的な取得費を計算しましょう。
まとめ
建物の取得費は所得税の金額にも大きな影響があるので、その金額が不明な場合は慎重に検討したい項目です。
購入代金だけでなく、購入時の諸費用や改良費なども含まれるため、幅広い支出を漏れなく計上することが節税につながります。
土地や建物を一括購入したケースなど取得費の計算は複雑で個々の状況により最適な方法が異なりますので、無用な税負担を避けるためにも、ぜひお気軽にお問い合わせください。


