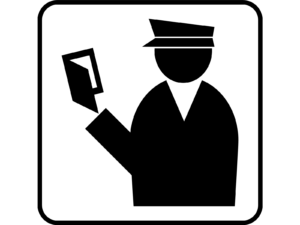中小企業も配当したい!中小企業のための配当実務入門

会社の利益が順調に伸びてくると、「そろそろ株主へ配当を出して、利益を還元したい」と考える経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
配当は、株主への大切な利益還元の手段です。
しかし、実際に配当を行うには、会社法や税務の視点から、さまざまなルールや注意点を押さえる必要があります。
特に、「みなし配当」や「分配可能額」といった聞き慣れない専門用語につまずいてしまう方も少なくありません。
今回は、後になって思わぬ税務リスクや会社法上の問題に直面しないように、中小企業が配当を適切に行う際のポイントを解説します。
目次
配当とは何か?
配当の定義と種類
配当とは、会社が稼いだ利益の一部を、その会社の株主に分配することです。
会社法上は「剰余金の配当」と呼ばれ、文字通り会社に蓄積された剰余金(利益や資本から生じた余剰資金)を原資とします。
以前の商法では配当は原則年1回に限定されていましたが、現在の会社法では、定時株主総会はもちろん、臨時株主総会の決議によっても配当が可能になり、回数に制限はなくなりました。
これにより、企業の状況に応じて柔軟な利益還元ができるようになっています。
配当の原資は、一般的に「利益剰余金」(会社がこれまで稼いできた利益の蓄積)が使われますが、「その他資本剰余金」(資本取引によって生じた余剰金)からも配当を行うことが可能です。
ただし、資本剰余金を原資とする配当の場合、税務上の取り扱いが異なります。
いわゆる「みなし配当」として扱われる部分が出てくるため、後述する詳細を必ず確認しましょう。
例えば、資本剰余金を原資とした配当を受け取った個人株主にとっては、その一部が「資本の払い戻し」として譲渡所得の対象となり、残りが「配当所得」と認識されます。
一方、配当金を支払う会社側にはみなし配当に対する源泉徴収義務が発生したり、支払通知書の作成・交付などの税務処理が生じます。
みなし配当
「みなし配当」とは、文字通り「配当ではないけれど、税法上は配当とみなして課税しますよ」という特殊な概念です。
実際の配当の形式をとっていなくても、実質的に会社の利益が株主に移転したと見なされる場合に適用されます。
中小企業で「みなし配当」が発生しやすい典型的なケースは以下の通りです。
- 資本剰余金を原資とする配当
前述の通り、資本剰余金から配当を行った場合、その一部がみなし配当となります。 - 自己株式の取得
会社が株主から自社の株式を買い取る際、その取得価額が「資本金等の額」(税法上の資本金に相当する金額)を超える部分がみなし配当の金額となります。 - 会社解散時の残余財産の分配
会社が解散し、残った財産を株主に分配する際、払い込んだ資本金等の額を超える部分がみなし配当とされます。 - 有償での出資の払い戻し・減資
会社から株主に資金を支払って資本金の額を減少させたり、出資金を株主に返還したりする際に、払い込んだ出資金を超える部分。
例えば、会社が株主から自己株式を時価で取得したとしましょう。
このとき、自己株式を買い取った金額のうち、その株式に対応する「資本金等の額」を超える部分については、株主が会社から利益を受け取ったものと見なされ、「みなし配当」として課税対象となります。
この「みなし配当」の部分は、通常の配当と同様に、所得税(個人の場合)または法人税(法人の場合)の課税対象となり、会社側には源泉徴収義務が生じます。
配当の上限額について
会社法では配当金額に対する規制が存在します。
これは会社の財産が過度に流出し、債権者や会社自身が困窮してしまうことを防ぐためのセーフティネットとして機能します。
分配可能額
配当を行うにあたって重要なのが、「配当可能額(分配可能額)」の存在です。
これは会社法によって定められた、会社が株主に対して配当できる上限金額になります。
配当可能額は、簡単に言うと会社の剰余金(利益剰余金や資本剰余金など)から、自己株式の帳簿価額などの一定の金額を控除した残額が上限となります。
実務上、配当可能額を計算する際は、以下の2つの段階を踏んで算定します。
- 直近の決算日時点の剰余金の額を把握する。
- その決算日から実際に配当を行う時点までの財産の変動(自己株式の取得・処分、減資、期中の利益の発生や損失など)を加味して、最新の剰余金を計算する。
純資産額300万円規制
中小企業が配当を行う際には、純資産額300万円規制にも注意が必要です。
会社の純資産額が300万円未満となる場合は剰余金の配当はできないこととなっています。
これも会社の最低限の財政的基盤を守り、債権者や会社存続へのリスクを防ぐためのルールです。
したがって、配当実施前には、純資産残高が300万円を下回っていないか必ず確認しましょう。
配当を実施するための手続き
配当を実際に実施するには、会社法に基づいた手続きを踏む必要があります。主な流れは以下の通りです。
- 配当可能額の確認
まず、前述の通り、配当を行う時点での配当可能額を会社法のルールに則って計算します。 - 機関決定(取締役会または株主総会)
配当を実施するには、会社法に基づいた適切な機関決定が必要です。- 原則:株主総会の決議
剰余金の配当は、原則として株主総会の普通決議によって決定されます。
多くの中小企業ではこの形式が一般的です。 - 例外:取締役会の決議(取締役会設置会社の場合)
会社法上、会計監査人や監査役会を設置しているなどの要件を満たした株式会社は株主総会での決議を要せずに取締役会で配当を決議することが可能です。
中小企業ではあまりないケースですので詳細は割愛します。
- 原則:株主総会の決議
- 配当財産の種類や金額などの決定
- 配当財産の種類
金銭など。 - 配当財産の割り当てに関する事項
一株当たりの配当金の金額や配当金の総額を決定します。 - 配当が効力を生ずる日
株主が配当金を受け取る権利が確定する日。
- 配当財産の種類
- 配当金の支払いと税務処理:
- 確定した金額を各株主へ支払います。
- 支払時に源泉徴収を行い、所轄の税務署へ納付します。
- 後述する支払調書の提出も忘れてはいけません。
配当に関する税務
配当は利益還元であると同時に、税務上も非常に重要な取引です。会社側と株主側、双方で適切な税務処理が求められます。
配当支払い会社側の源泉徴収義務
非上場株式の配当を支払う会社には、20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)の源泉徴収義務があります。
つまり、会社は株主に配当金を支払う際に、この税額を差し引いて支払い、差し引いた税金を所轄の税務署へ納付しなければなりません。
この源泉徴収税額の納付期限は、原則として配当の支払日(効力発生日)の翌月10日です。
税務署への「支払調書」提出
配当を支払った会社は、税務署に対して「配当、剰余金の分配、金銭の分配および基金利息の支払調書」(法定調書の一種)を提出する義務があります。
この支払調書は、配当の支払日または確定日から1か月以内に、所轄の税務署へ提出する必要があります。
提出の際には、「法定調書合計表」と合わせて提出が必要です。
みなし配当の場合の通知義務
前述の「みなし配当」が発生する取引(自己株式の取得や減資など)を行った場合、会社は、そのみなし配当を受け取った株主に対して「支払通知書」を送付する義務があります。
この通知書には、株主が自身の確定申告を適切に行うために必要な情報、例えば「配当等とみなされる金額」や「資本金等の額から成る部分」などを明記する必要があります。
これにより、株主は自己株式の売却などによって得た金額のうち、どの部分が「配当」とみなされ、どの部分が「資本の払い戻し」に当たるのかを正しく把握し、税務申告を行うことができます。
こちらも合計表とともに提出します。
配当を受け取った側の税務処理
個人の株主の場合
個人が非上場会社の配当を受け取った場合、その配当は原則として「配当所得」となり、総合課税の対象となります。
総合課税の場合、他の所得(給与所得や事業所得など)と合算され、所得税の税率が適用されます。
ただし、一定の条件を満たせば「配当控除」を適用できる場合があります。
これは、法人段階で課税された利益が個人段階でも課税される「二重課税」を緩和するための制度です。
法人の株主の場合
法人が他の会社から配当を受け取った場合、原則として「受取配当等の益金不算入制度」が適用されます。
これは、配当を受け取った法人の益金(収益)に算入しない、つまり課税対象としないという制度です。
この制度も「二重課税」を排除するために設けられています。
しかし、株式の保有割合や保有期間などの条件によって、益金に算入しない割合(不算入割合)が変わるため注意が必要です。
例えば、完全子会社株式に係る配当であれば全額が益金不算入となりますが、その他の場合は段階的に益金不算入の割合が定められています。
注意点
違法配当
前述の配当可能額を超える配当を行ってしまった場合、それは「違法配当」となります。
違法配当が行われた場合、配当を行った取締役や執行役、そして不当に配当を受け取った株主が、連帯して会社に対して損害賠償責任を負うリスクがあります。
例えば、会社の財産が減少し、債権者への弁済が困難になった場合などには、会社や債権者から損害賠償請求がなされる可能性があります。
配当の確定から1年以内に実際に支払いがなかった場合
配当の確定から1年以内に実際に支払いがなかったとしても、その1年が経過した時点で「支払があったもの」とみなされ、源泉徴収義務が発生します。
翌月10日までに納付しなければなりませんので注意が必要です。
まとめ
中小企業でも配当金を支払っている会社は多いものです。
しかし、そこには会社法や税法という複雑なルールが絡み合っており、これらを無視したまま進めてしまうと、損害賠償責任や追加課税といった思わぬトラブルの火種になりかねません。
特に、みなし配当や分配可能額を誤解していると、大きなリスクを招く可能性があります。
配当が確定する日を何時にするかによって受け取る側の課税実務にも影響が出てきますので、不安な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。