インボイスがないと控除できない?なくても控除できる?~インボイス不要取引と注意点~
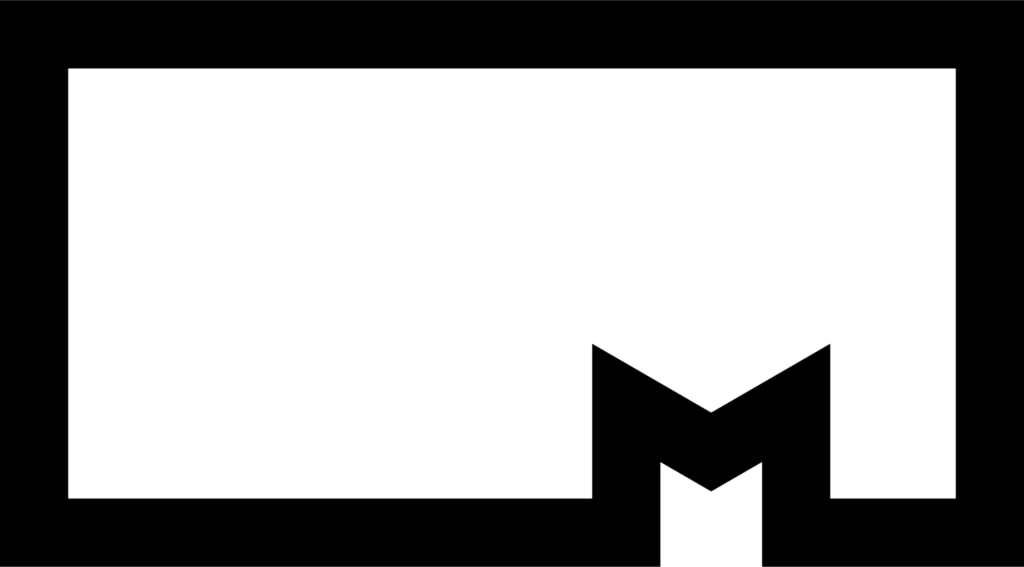
令和5年10月に幕を開けたインボイス制度。
『インボイス保存がマスト』と思いきや、旅費や少額取引など“インボイス不要”で仕入税額控除ができる特例も多く用意されています。
今回は、帳簿だけで済む特例の使い方と陥りがちな落とし穴を解説します。
目次
インボイス不要取引
インボイス制度は複数税率でも消費税の納税額を正しく計算するために、物やサービスの消費税率や消費税額を記載したインボイスを基に計算する制度です。
基本的には預かった消費税額から控除する仕入税額には請求書や領収書などのインボイスが必要ですが、3万円未満の公共交通機関運賃など次のような一定の取引にはインボイスの保存は必要ありません。
- 3万円未満の公共交通機関運賃
- 従業員への日当や宿泊費精算、通勤手当
- 3万円未満の自販機・コインパーキング利用
- 郵便切手を対価とする郵便サービス
- 古物商などが仕入れる古物・質物 など
令和11年9月30日まではどんな取引でも1取引税込1万円未満であればインボイスが不要となる少額特例も併用できます。
ただし少額特例は基準期間の課税売上1億円以下というハードルがありますので、たまたま2年前に固定資産の売却などがあり、課税売上が1億円を超えてしまった場合などは注意が必要です。
帳簿のみ保存特例の要件と記載方法
上記の特例では、インボイスがなくても控除を取れる代わりに、帳簿へ一定事項の記載が要件となっています。
特例以外でも帳簿への記載が必要な事項として①取引年月日、②相手方名称、③取引内容、④金額、⑤軽減税率の対象かどうかがありますが、特例を適用する場合はどの特例に該当するかも合わせて記載します。
例えば3万円未満の公共交通機関特例を適用する場合には『3万円未満の公共交通機関特例』や『3万円未満の鉄道料金』などと記載し、3万円未満の自販機などの仕訳に適用する場合は『自販機』や『ATM』などと記載しましょう。
免税事業者からの仕入れ―80%控除の経過措置
令和8年9月30日までは、免税事業者との取引でも80%の仕入税額控除が認められる経過措置が認められています。
インボイス制度では本来、インボイスの保存がある場合のみ仕入税額控除を認めていますが、この経過措置の間はインボイスの保存が無くとも、区分記載請求書の保存があればその税額の80%を控除できる制度となっています。
免税事業者からの仕入でも80%控除できるのは令和8年9月30日までとなっており、その後令和11年9月30日までは50%に減額され、令和11年10月1日以後は本来の制度として仕入税額控除ができないこととなります。
またクラウド会計ソフトに備わる取引先マスター機能は、インボイスの登録事業者かどうかをシステムが判定してくれます。
登録番号を取引先マスターに一度入力するだけで、自動照合が走り、適格か非適格の判定が行われますので仕訳の都度確認する作業は軽減され効率的に記帳業務が進むでしょう。
注意点
クレジットカード明細はインボイスの代わりにならない
カード利用明細には店名・金額が載っていても、登録番号や税率の記載がないためインボイス要件を満たしません。
控除にはレシートか領収書(簡易インボイス)の保存が不可欠です。
紙レシートを失くしやすい昨今は、決済直後にスマホで撮影し、クラウド会計に画像連携→OCRで税率自動読取→原本は月次で箱へ投げ込む“ワンストップ”運用が省力化の鍵。スキャナ保存要件の緩和を活用し、タイムスタンプ自動付与アプリで60日以内要件をクリアすると、紙の山から解放されます。なおカード明細とレシート画像を突合するリコンシリエーション機能を持つ会計ソフトを選べば、調査時に“二重証憑”として信頼性がグッと高まります。
簡易課税制度や2割特例の場合はインボイスは必要なし
簡易課税制度や2割特例を適用している事業者は、原則としてインボイスの保存が不要です。
これらの制度は、課税仕入れに関する消費税額の計算を簡略化するため、インボイスがなくても仕入れ税額控除を受けられます。
ただし法人税や所得税の所得の計算上、これまでどおり領収書や請求書の保存は必要です。
まとめ
インボイス制度は、特例や経過措置が多く、判断に迷うケースも少なくありません。
保存が必要な書類や、帳簿への記載方法など、通常とは異なる取り扱いをとるものもありますので各取引の事務処理には注意が必要です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


