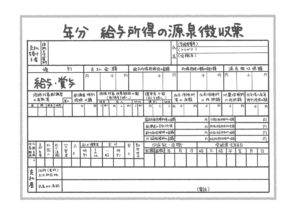自宅の敷地の評価が劇的に下がる!居住用小規模宅地の基礎

2025年7月に公表された最新の路線価は全国平均で前年を上回り、都市部では5%超の上昇地点も珍しくありません。
評価額が上がれば、そのまま相続税の課税ベースも膨らむため、今後は“宅地の評価をいかに下げるか”がこれまで以上に重要なテーマになります。
そこで鍵となるのが、最大330㎡まで土地評価を80%圧縮できる「居住用の小規模宅地等の特例」。
今回は、この特例を活用するためのポイントを解説します。
目次
小規模宅地の特例とは
小規模宅地等の特例は、被相続人の事業または居住の用に供されていた宅地等について、一定の面積まで相続税評価額を最大80%(貸付事業用なら50%)減額できる制度です。
限度面積は区分ごとに定められており、特定居住用330㎡と特定事業用400㎡を組み合わせれば合計730㎡まで評価減が可能。
ただし貸付事業用を混在させると換算式が変わり、200㎡上限換算がかかる点に注意が必要です。
国税庁 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
複数の宅地等で小規模宅地の特例の適用を受けられる場合は、限度額まででしたら複数の宅地に適用が可能です。
特定居住用宅地に該当する要件は下記のとおりです。
| 区分 | 対象となる宅地 | 取得者 | 取得者ごとの主な要件(抜粋) |
|---|---|---|---|
| ① 被相続人居住用宅地 | 被相続人が居住していた宅地(老人ホーム入所前の自宅を含む) | 1. 配偶者 | 追加要件なし |
| 2. 同居親族(相続開始時に同一家屋に居住) | 相続開始直前から申告期限(10か月後)まで継続居住+その宅地を相続開始時から申告期限まで保有 | ||
| 3. 上記以外の親族 | 以下 (1)〜(6) をすべて満たす (1) 外国居住などの居住制限納税義務者などでない (2) 被相続人に配偶者がいない (3) 同居相続人がいない (4) 相続開始前3年以内に関連者所有家屋に居住歴なし (5) 相続開始時に自宅を所有したことがない (6) その宅地を相続開始時から申告期限まで保有 | ||
| ② 生計一親族居住用宅地 | 被相続人と生計を一にする親族が居住していた宅地 | 1. 配偶者 | 追加要件なし |
| 2. 生計一親族 | 相続開始前から申告期限まで継続居住+ その宅地を申告期限まで保有 |
また遺産分割協議が成立していることが原則であり、未分割の場合、原則として特例は適用できません。
未分割の状態で申告期限を迎えてしまった場合は相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておきましょう。
手続き
相続税申告書の「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」に必要事項を記載し、下記の書類を添付して提出します。
- 遺言書または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書
- 戸籍謄本や住民票の写し(被相続人・相続人の関係や居住状況を証明するため)
- その他、要件を証明する書類(例:別居親族の場合は持ち家がないことの証明など)
注意点
適用には相続人全員の同意が必要
同意は、相続税申告書の「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」の同意欄に小規模宅地の特例を適用可能な宅地等を取得した相続人全員の氏名を記載することで足ります。
自署や押印は不要ですが、全員の同意がなければ特例は適用できません。
特例の適用対象となる宅地等は限度面積があるため、複数の宅地や相続人がいる場合、どの土地に特例を適用するかで相続税全体の負担配分が大きく変わります。
特定の相続人だけが有利になったり、他の相続人が不利益を被ることを防ぐため、公平性の観点から全員の同意が求められています。
一方、どの宅地に小規模宅地の特例を適用させるかまとまらず、同意が得られない場合は特例は認められません。
その結果、土地の評価額が減額されず、全体の相続税額が大幅に増加します。
例えば、330㎡・1億円の自宅土地で特例が適用できない場合、本来2,000万円で済む評価額が1億円のままとなり、税率30%なら2,400万円もの税負担増となるケースもあります。
配偶者の税額軽減との比較
配偶者には配偶者の税額軽減特例があるため1億6000万円までの相続財産には相続税が課されません。
このため配偶者が取得した宅地で小規模宅地の特例を適用してしまうと、相続税が実質ゼロになることが多い一方、限度面積を消費してしまうデメリットも出てきます。
そのため配偶者が評価減不要な資産を取得し、事業を承継する子が特例を活用する方が有利となる場合があります。
配偶者自身の相続時に小規模宅地の特例が適用できるかなど二次相続も見据えた上で誰が相続するかを検討することが重要です。
遺留分侵害額請求と小規模宅地の適用外リスク
2019年改正民法で遺留分が金銭債権化された結果、その履行のため宅地を移転すると「相続または遺贈」による取得とはならないため特例対象外となります。
あくまで小規模宅地の特例の適用を受けたい場合は、遺留分対策を行ったうえで遺言を作成しておくなど事前準備が重要です。
老人ホーム入所でも特例OK
被相続人が特別養護老人ホームへ入所し自宅が空き家になっていた場合でも、要介護認定を受けていること、用途変更していないこと等を満たせば居住用宅地として80%減が認められます。
要支援認定の申請中であってもその後認定されれば、小規模宅地の特例の適用は可能です。
まとめ
小規模宅地等の特例は、ちょっとした手続きの違いや相続人間の調整によって、相続税の負担が大きく変わる非常にデリケートな特例です。
早期に候補地と取得者を確定し、相続人間で合意をしておくことが重要です。
「うちの場合は特例が使えるのか?」「遺産分割や相続人の同意が得られるか不安」「具体的にいくら節税できるのか知りたい」など、少しでもご不明な点やご心配があれば、どうぞお気軽にご相談ください。