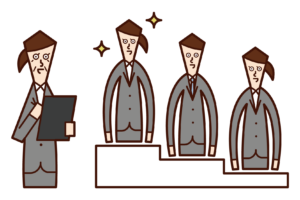見逃し注意!平成21・22年取得土地の1,000万円控除

リーマンショック後の景気対策として導入された「平成21年・22年取得土地等の譲渡所得の1,000万円控除」。
取得から相当の期間が経っているため、申告の際にこの特例を思い出せず適用漏れするケースが少なくありません。
しかも、取得日の判定一つで適用の可否が変わるため、実務では契約日か引渡日か、所得税と法人税の違いなどを丁寧に整理する必要があります。
今回は、特例の概要から注意すべき論点までをわかりやすく解説します。
特例の概要と要件
概要
リーマンショック後の不動産市場のてこ入れとして設けられた制度で、平成21年(2009年)または平成22年(2010年)に取得した国内の土地および土地の上に存する権利を売却した場合、長期譲渡所得から最大1,000万円を特別控除できます。
譲渡所得が1,000万円未満なら、その金額が控除額=つまり“ゼロまで”引けるイメージです(マイナスまでは行きません)。
対象税目は所得税(譲渡所得)で、平成21年取得分は平成27年以降の譲渡、平成22年取得分は平成28年以降の譲渡が対象となります。
加えて、法人にも同趣旨の特例が用意されています。
個人向け(所得税)のこの特例と並走して設計されたもので、事案によっては検討対象になり得ます。
さらに、平成21年度改正の「先行取得土地等の特例」(圧縮記帳)との関係でも、要件を満たせば本1,000万円控除の適用対象になり得る点が実務トピックです。
要件
- 対象資産
・国内の土地および土地の上に存する権利が対象となり、建物そのものは含まれません(売買が一体でも“土地等”部分のみが対象)。 - 取得時期
・平成21年1月1日〜平成22年12月31日の間に取得していること。
・譲渡時期は、平成21年取得分→平成27年以降, 平成22年取得分→平成28年以降(譲渡年の1月1日現在で5年超保有)となるため「取得日」の判定が重要です。
— 個人の所得税では、原則は引渡日だが、条件を満たせば契約(効力発生)日基準も選択可となります。
したがって、契約日が平成22年12月・引渡が平成23年1月といったケースでも、契約日基準で21・22年取得に該当させられる余地があります。
— 上記は個人の取得日の考え方となり、法人の取得日は原則「引渡日」(契約日基準は不可)となります。
法人の場合、30%以上の代金を先に支払った場合など例外はあるものの、基本的には引渡日ベースで判断します。
法人側での同特例を検討する場合は、この違いに要注意です。 - 対象者・適用除外となる取得形態
・特別の関係がある者(親子・夫婦等)からの取得は除外。
・相続・遺贈・贈与・交換・合併・分割・出資等による取得も除外。 - 他の特例との重複適用の禁止など
・収用特例、事業用資産の買換え、居住用3,000万円特別控除 等、他の譲渡所得特例を同じ譲渡で使う場合は本特例は使えません。
どの特例を採用するのが最適か、比較検討が欠かせません。
・法人の場合は、清算中であったり特定資産の買い替えの場合の圧縮記帳の特例などの適用を受けているケースではこの特例の適用はありません。
申告実務と必要書類
特例の適用には、取得時点での届出や申請は不要ですので非常に使い勝手の良い特例になります。
実際の手続きは譲渡が発生した際の確定申告時に行い、その際に必要書類を添付します。
具体的な提出書類としては、譲渡所得の内訳書(土地・建物用)および売買契約書や登記事項証明書など、取得日を客観的に示す書類です。
法人の場合は、法人税申告書に「別表10(5)」の明細書を添付する必要があります。
これにより、どの土地が特例の対象であるかが明確化されます。
個人と法人で異なる扱い
要件でも記載しましたが、個人と法人との最大の違いはいつを取得日とするかの判定に違いとなります。
個人の場合、契約日基準か引渡日基準かを選択できる柔軟性があるため、税務上有利な判定が可能です。
例えば、平成22年末に契約し、翌年引渡しのケースでは契約日基準を使えば特例対象に含められることになります。
一方、法人では原則として「引渡日」が取得日となり、契約日基準は適用されません。
法人における例外は、代金の30%以上を前払いしているケースなどに限られます。
法人がこの特例を適用するケースの場合はその土地の取得日がいつになるのか気を付けて判定ましょう。
まとめ
平成21・22年取得土地等の譲渡所得1,000万円控除は、適用の有無で税負担が大きく変わる重要な特例です。
しかし、取得日の判定基準や個人・法人の違いを誤解すると、適用漏れや否認につながります。
譲渡案件が出たら必ず取得年を確認し、適用漏れのないように注意しましょう。
確定申告に際して不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。