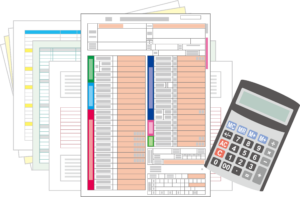サラリーマンが親の事業を相続したら?知っておくべき所得税の手続き

「父が個人事業主だったけれど、私はサラリーマン。事業のことはよくわからない…」
「相続した事業をどう処理すればいいの?このまま続けるべき?それとも廃業?」
個人事業主だった親族が亡くなり、その事業を相続することになったサラリーマンの方から、このようなご相談をよくいただきます。
普段は給与所得しかなく、確定申告にも馴染みがない方にとって、突然降りかかる事業の相続は大きな負担となります。
消費税の取り扱いについては、以前詳しく解説していますので、こちらの記事もぜひご参照ください。
今回は、サラリーマンが個人事業を相続した場合の所得税に焦点を当て、必要な手続きや注意点を解説します。
目次
税務上の届け出・申告期限
相続によって事業を引き継ぐ後継者にとって、税務上の届け出関係は最初に対応しなければならないものの一つです。
期限が設定されているものもあり、間に合わないと希望する時期からの適用を受けられない特例もありますので注意が必要です。
必要な届出書類と期限
相続により事業を開始した場合に提出する届出書として、主なものは以下のとおりです。
各届出書はすべて必須というわけではありませんので、ご自身の状況に応じて必要なものを選択して提出してください。
- 個人事業の開業・廃業等届出書:相続後、原則として1か月以内に提出
- 所得税の青色申告承認申請書:青色申告を希望する場合、相続があったことを知った日に応じて下記の期限内に提出
- その死亡の日がその年の1月1日~8月31日まで:死亡の日から4か月以内
- その死亡の日がその年の9月1日~10月31日まで:その年の12月31日まで
- その死亡の日がその年の11月1日~12月31日まで:その年の翌年の2月15日まで
- 青色事業専従者給与に関する届出書:開業の日から2月以内
- 給与支払事務所等の開設届出書:開設の事実があった日から1か月以内
- 減価償却資産の償却方法の届出:新規開業の年分に係る所得税の確定申告期限
- 所得税・復興特別所得税の振替納税手続き:振替納税を利用する国税の納期限
これらの届出書の提出期限を過ぎてしまうと、青色申告特別控除などの税務上の優遇措置を受けられなくなる場合があります。
相続発生後は速やかに必要な手続きを確認し、期限内に提出するよう心がけましょう。
減価償却資産の承継
被相続人が事業で使用していた機械や車両、建物などの減価償却資産については、後継者が新たに購入したものとしてゼロから減価償却を始めるわけではありません。
以下の項目を被相続人からそのまま引き継ぎます。
- 取得時期
- 取得価額
- 帳簿価額
- 耐用年数
つまり、亡くなった方の償却履歴をそのまま引き継いで、続きから償却を開始するイメージですが、償却方法は少し異なります。
被相続人が旧定額法・旧定率法で償却していた資産は、相続後は定額法・定率法(現行制度)で償却することになります。
また上記の減価償却資産の償却方法の届出を提出した場合は、選択した償却方法により償却します。
固定資産税の扱い
事業用資産にかかる固定資産税の取り扱いは、被相続人の死亡日(相続開始日)と納税通知書の送達時期によって大きく変わります。
この判断を誤ると、準確定申告や相続人の確定申告で経費の計上漏れや重複計上が発生する可能性があります。
基本的な考え方
固定資産税の必要経費算入時期は、原則として、納税通知等により納付すべきことが具体的に確定したときとされています。
年の中途で死亡した場合には、その死亡のときまでに確定したものに限られます。
パターン別の取り扱い
【パターン1:相続開始前に納税通知書が届いている場合】
納税通知書が死亡前に届いている場合、被相続人の準確定申告では以下の3つの方法から選択できます。
- 全額を準確定申告で必要経費算入
- 納期到来分のみを準確定申告で必要経費算入
- 実際に納付した分のみを準確定申告で必要経費算入
相続人の確定申告では、準確定申告で計上しなかった残額を必要経費に算入します。
【パターン2:相続開始後に納税通知書が届く場合】
相続開始時には納税通知がされていませんので、被相続人の準確定申告における不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。
この場合、固定資産税の全額を相続人の確定申告で必要経費に算入します。
相続人は以下の方法から選択可能です。
- 全額を相続発生年度の確定申告で必要経費算入
- 納期到来分のみを各年度の確定申告で必要経費算入
- 実際に納付した分のみを各年度の確定申告で必要経費算入
相続開始前に納税通知書が届いている場合は、被相続人の準確定申告や相続人の確定申告の状況に応じて、最適な方法を選択しましょう。
相続税での取り扱いとの違い
注意すべき点として、相続税では取り扱いが異なります。
固定資産税の賦課期日はその年の1月1日ですから、納期がまだ到来していないものであっても、全額を債務として相続税の課税価格の計算上控除することができます。
注意点
個人事業主の相続で気を付けなければならないポイントが、引き継いだものの事業がうまくいかず、相続開始の日から10か月以内に廃業する場合の小規模宅地等の特例への影響です。
小規模宅地等の特例は、事業用や居住用の宅地について、相続税の課税価格を大幅に減額できる制度です。
事業用宅地(特定事業用宅地等)の場合、400㎡まで80%の減額が可能です。
相続開始の日から相続税の申告期限(10か月)までの間に事業を廃業してしまうと、小規模宅地等の特例の適用要件を満たさなくなる可能性があります。
主な適用要件:
- 相続税の申告期限まで事業を継続していること
- 申告期限まで事業用宅地を保有していること
相続税申告の際に事業用資産の小規模宅地の特例の適用を受けている(受けようとしている)場合、相続開始の日から10か月以内に事業を廃業してしまうと数百万円から数千万円の追加税負担が発生する可能性があります。
能性があります。
事業用小規模宅地の特例の適用して相続税を申告している場合は、相続税申告期限まで(最低10か月間)は事業継続を維持できないかなど慎重に検討しましょう。
まとめ
個人事業主の相続では、税務手続き、減価償却資産の承継、固定資産税の取り扱い、さらには廃業タイミングまで、多岐にわたる論点があります。
これらの手続きを怠ったり、誤った処理をしたりすると、青色申告が適用できなかったり、小規模宅地等の特例の適用除外による相続税増加といった思わぬ税負担が生じることもあります。
当事務所では、相続税だけでなく、所得税や消費税まで含めた、個人事業主の相続に関する総合的なサポートを提供していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。