相続で事業を引き継いだ個人事業主の注意点【消費税編】
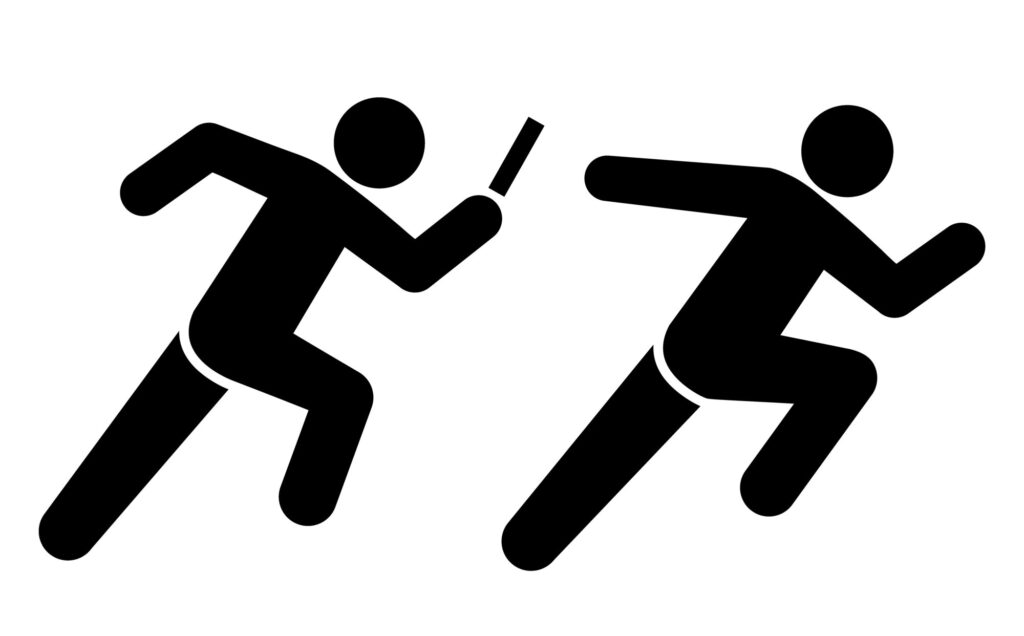
個人事業主として事業を営んでこられた方が亡くなった場合、相続が発生します。
相続税のことはもちろん気になりますが、実は消費税についても注意が必要です。
亡くなった方が消費税の課税事業者であった場合、相続人は様々な手続きや判断を迫られることになります。
そこで今回は、個人事業主の皆様が相続発生時に知っておくべき消費税の重要ポイントをまとめました。
この記事を読めば、
- 相続開始年の消費税はどうなるのか
- 簡易課税の届け出は引き継がれるのか
- インボイス制度への対応はどうすればいいのか
など、気になる疑問を解消することができます。
ぜひ最後までお読みいただき、今後のためにお役立てください。
目次
相続開始年の消費税の取り扱い(納税義務の判定)
相続が開始した年度の消費税について亡くなった方(被相続人)と事業を引き継いだ方(相続人)に分けて見ていきましょう。
被相続人
被相続人が課税事業者だった場合、相続人が相続開始日から4ヵ月以内に消費税の準確定申告を行う必要があります。
被相続人の納税義務の判定は以前のブログで解説していますので確認してみてください。
その年の1月1日から亡くなった日までの取引が申告の対象になります。
付表7 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書を添付して準確定申告書を提出した場合は個人事業者の死亡届出書の提出があったものとみなされます。
相続人
事業を承継した相続人がもともと課税事業者だった場合は自身の消費税と承継した事業に係る消費税を合わせて納付することとなります。
しかし消費税の課税事業者でなかった場合(サラリーマンなど)や事業を行っているが基準期間の課税売上高が1000万円以下などの理由で消費税を納める必要がなかった場合は注意が必要です。
相続があった年については2年前の被相続人の課税売上高が1000万円を超えている場合は相続開始日の翌日から12月31日までの納税義務が生じますので翌年3月31日までの申告・納税が必要です。
相続があった年の翌年・翌々年については、その年の2年前の被相続人の課税売上高と相続人自身の課税売上高の合計額が1000万円を超える場合はやはり納税義務が生じますので上記と同様に申告・納税が必要になってきます。
国税庁 No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
ただし相続財産が未分割の場合には、財産の分割がなされるまでの間は各相続人が共同して事業を承継しているものとして取り扱われます。
この場合に各相続人のその課税期間の2年前の年の課税売上高は、その年の2年前の被相続人の課税売上高に法定相続割合を乗じて計算した金額となります。
注意点
亡くなった方から引き継ぐ事業用資産の取り扱い
被相続人の事業用財産(棚卸資産や事業用不動産、事業用動産など)も相続により相続人に移転します。
相続により財産が移転した場合は、消費税の課税対象の取引とはなりませんので被相続人側での課税売上、相続人側での課税仕入には該当しません。
特定遺贈等により事業を承継した場合
事業を承継した相続人の納税義務の判定で被相続人の2年前の課税売上高により判定される旨はご案内のとおりですが、この特例は相続により事業を承継したケースを指しています。
特定遺贈や死因贈与により事業を承継した場合は被相続人の2年前の課税売上高は関係なくなりますので、受遺者等の2年前の課税売上高のみにより判定されます。
相続人が簡易課税制度を選択するための届出書の提出期限
被相続人が簡易課税制度を選択していた場合でも、相続によりその選択が相続人に承継されることはありません。
課税事業者でなかった相続人が、今回の相続をきっかけに簡易課税制度を選択したい場合は原則として相続開始年の12月31日までに簡易課税制度選択届出書を所轄税務署に提出する必要があります。
ただし被相続人が12月に亡くなった場合は、その提出期限は翌年2月末までとなります。
簡易課税制度の課税売上高判定の対象
その年の消費税について簡易課税制度の適用を受けられるかどうかは2年前の課税売上高が5000万円を超えているかどうかで決まります。
この場合の2年前の課税売上高には被相続人の2年前の課税売上高は含まれず相続人の2年前の課税売上高だけで判定されます。
インボイス制度
インボイスの発行事業者であった個人事業主が亡くなった場合には適格請求書発行事業者の死亡届出書を税務署に提出しなければなりません。
亡くなった個人事業主の登録番号は死亡届出書が提出された日か死亡日から4か月のどちらか早い日でその効力が失われてしまいます。
本来であれば効力を失った登録番号ではインボイスにはならないところですが、事業を承継した方がインボイスの発行事業者に登録するまでの間、インボイスを発行できないとなると取引先が困ってしまいますので特例が設けられています。
インボイスの発行事業者が亡くなった日から4か月の間は被相続人の登録番号を使用してインボイスを発行することができます。
この間に事業を承継した相続人はインボイスの登録申請を進めましょう。
また相続の免税特例で課税事業者となる場合はインボイスの2割特例は使えないこととなりますので間違って適用しないようにしましょう。
まとめ
課税事業者だった個人事業主に相続が発生したケースでは事業を承継した相続人に消費税の納税義務が生じることがあります。
一方もともと事業を営んでいない相続人の方が生前に事業承継した場合は最大2年間、消費税の免税期間があります。
将来的に事業を承継する予定がある場合は相続により引き継ぐよりも生前に承継しておく方が承継もスムーズに進みますので検討してみてはいかがでしょうか。
筒井会計事務所では個人事業主の方の事業承継についてもご相談を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

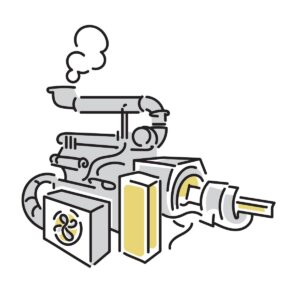

“相続で事業を引き継いだ個人事業主の注意点【消費税編】” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。