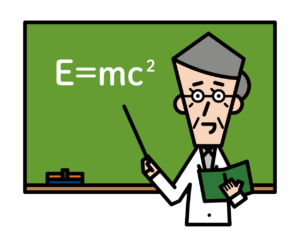中小企業の社長必見!寄付と経費の“税務上の境界線”

中小企業の税務において、「寄付金」とみなされる取引は、極めて慎重な取扱いが求められる分野の一つです。
たとえば地域団体への支援や関係先への援助行為は、企業の社会的責任や地域貢献の観点からは意義深いものですが、税務上の視点では「損金不算入」とされるリスクが常に伴います。
特に、寄付金の範囲や損金算入の可否、他の経費区分との違い、さらには経済的利益の無償供与といった論点は、実務担当者が誤認しやすいポイントです。
今回は、寄付金の税務上の定義や種類、具体的な該当事例、他の経費区分との違い、寄付金とされないための実務対応など解説します。
目次
寄付金の定義
法人税法上、寄付金とは「法人が対価を得ることなく他者に対して行う金銭その他の資産または経済的利益の無償の供与」をいいます。
ここで重要なのは、「対価性」と「事業関連性」の有無です。
すなわち、事業活動との直接的な関係がなく、見返りの得られない支出は、原則として寄付金として取り扱われます。
寄付金に該当する場合、当該支出は損金算入が制限され、一定額以上が損金不算入となることが原則です。
企業としての社会貢献活動や慈善的行為は尊重されるべきものですが、税務上は「経済的実質」に基づいて判断が行われます。
企業の意図や動機が善意によるものであっても、それが対価性や事業関連性を欠く場合、寄付金とされるリスクは排除できません。
寄付金の種類ごとの損金算入範囲と具体例
寄付金は、支出先や内容によっていくつかの種類に分類され、それぞれ損金算入の可否や限度額が異なります。
主な分類と特徴は以下の通りです。
(1) 指定寄付金
国や地方公共団体、または財務大臣が指定した公益性の高い団体等(日本赤十字社、国立大学法人等)への寄付金は「指定寄付金」とされ、全額が損金算入可能です。
たとえば、災害被災地への義援金として日本赤十字社に寄付した場合などが該当します。
(2) 特定公益増進法人等に対する寄付金
学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人など、一定の公益性を有する団体への寄付金は「特定公益増進法人等に対する寄付金」となり、所定の限度額の範囲内で損金算入が認められます。
特定寄付金の限度額:[(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375%)+(所得金額 × 6.25%)]×1/2
具体的には、私立学校への寄付や認定NPO法人への寄付がこれに該当します。
(3) 一般の寄付金
上記以外の団体等への寄付金は「一般の寄付金」として、より厳しい限度額の範囲内でのみ損金算入が可能です。
一般寄付金の限度額:[(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.25%)+(所得金額 × 2.5%)]×1/4
たとえば、寺院や町内会等への寄付がこれに該当します。
(4) 国外関連者・完全支配関係法人への寄付金
100%支配関係にある法人間や国外関連者への寄付金は、原則として全額損金不算入となる特例が設けられています。
グループ会社間取引や海外子会社への支援を検討する際には、特に注意が必要です。
このように、寄付金の種類ごとに損金算入の可否や限度額が異なるため、支出先や内容を正確に分類した上で処理することが実務上不可欠です。
なお、寄付金は「現金主義」により、実際に支出があった事業年度にのみ損金算入が認められます。
決算直前の寄付決定などで、支出日と会計処理日がずれる場合には注意が必要です。
寄付金として認定されやすい具体的な支出例
実務上、以下のような支出は、寄付金と認定される可能性が高いものです。
- 地域団体(町内会、自治会、PTA等)への金銭的支援
- 学校や公共施設に対する物品や金銭の無償提供
- 債権放棄(経済合理性を欠く場合)
- 市価を大きく下回る価格での財産譲渡
- 無償での役務提供や無利息貸付等(後述「経済的利益の無償供与」参照)
特に、債権放棄は注意を要する取引の一つです。
たとえば、経営難に陥った取引先に対して貸付金の回収を断念した場合、その行為が取引継続上の合理性や利益確保に資すると説明できなければ、当該金額は寄付金として損金算入が否認される可能性があります。
また、物品やサービスの無償提供についても、対価性や事業関連性が認められない場合には寄付金と判断されるリスクがあります。
これらの取引の多くは、「経済的合理性」と「対価性」の欠如が共通項であり、事前の検討と文書による裏付けが不可欠です。
市価から大きく乖離した価格での資産売買
- 市価より著しく低い価格での財産譲渡(例:時価1,000万円の不動産を100万円で譲渡した場合、差額900万円が寄付金とみなされる)
- 市価より著しく高い価格での財産購入(例:時価100万円の物品を1,000万円で購入した場合、差額900万円が寄付金とみなされる)
- 経済合理性を欠く債権放棄(例:資力がある相手に対する債権を放棄)
特に、親族会社間やグループ会社間での取引は、税務当局からみなし寄付金として指摘されやすい傾向にあります。
価格設定の妥当性や取引の経済的合理性を客観的に説明できる資料の整備が不可欠です。
経済的利益の無償供与(無利息貸付・無償サービス提供等)の寄付金該当性
寄付金の範囲には、金銭や物品の贈与だけでなく、「経済的利益」の無償供与も含まれます。
これは、法人が本来受け取るべき対価を受け取らずに他者に利益を与えた場合、その利益相当額が寄付金として取り扱われるという考え方です。
- 無利息での貸付(本来受け取るべき利息相当額が寄付金とみなされる)
- 無償での役務提供(たとえば、従業員を一定期間無償で他社に派遣した場合、その人件費相当額が寄付金とみなされる)
- 無償での施設・設備の貸与(使用料相当額が寄付金とみなされる)
これらは実務上見落とされがちですが、税務調査において指摘されるケースも多いため、注意が必要です。
広告宣伝費・交際費等との区別
寄付金との混同が生じやすい支出として、「広告宣伝費」および「交際費」があります。
これらはいずれも損金算入が認められる(交際費は一定制限あり)ため、実務上はこれらの区分に該当させることが企業にとって有利です。
たとえば、地域のイベントに対して金銭的支援を行い、その見返りとして企業名の掲載や物品提供等を通じて広告効果を得ている場合、当該支出は「広告宣伝費」として処理することが可能です。
一方、取引先や関係先との円滑な関係構築を目的として支出される飲食費や贈答品費用などは、「交際費」として整理されます。
ただし、交際費は原則として中小法人を除き一定の限度額があるため、処理方法には注意を要します。
いずれの費目も、「支出の目的」と「受けた経済的利益」が合理的に説明できるかどうかが判断基準となります。
寄付金とされないために必要な実務対応
税務調査等において、寄付金と認定されないようにするためには、支出の「対価性」および「事業関連性」があることを明確に証明する必要があります。
具体的には以下のような対応が求められます。
- 支出の目的および背景を記載した稟議書や社内決裁文書の作成
- 協賛内容を明記した契約書や請求書の保存
- 実際の広告効果や営業目的を示す証拠資料(写真・パンフレット等)の保存
- 債権放棄の場合は、合理的理由や取引継続上の必要性を説明した書面の作成
これらの資料を整備・保存しておくことにより、寄付金とされるリスクを大幅に軽減できます。
税務調査での指摘事例と実務上の注意点
税務調査においては、寄付金と広告宣伝費・交際費等との区分、みなし寄付金の認定、経済的利益の無償供与の有無などが重点的に確認されます。
たとえば、協賛金や見舞金、実質的な広告宣伝費との区分が曖昧な場合、寄付金認定されるリスクがあります。
過去の指摘事例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 地域イベントへの協賛金を広告宣伝費として処理していたが、実際には広告効果が認められず、寄付金と認定された
- 取引先に対する債権放棄が、取引継続上の合理性を欠くとして寄付金とされた
- 無利息貸付や無償サービス提供について、経済的利益の無償供与として寄付金課税が行われた
- グループ会社間での役員・従業員の出向において、給与負担金の精算を適切に行わなかったため寄付金認定された
このようなリスクを回避するためには、支出の目的や経済的合理性の説明責任を果たすことが不可欠です。
まとめ
企業の社会的責任や地域貢献として行う寄付行為は、理念として非常に意義深いものですが、税務上は全額が損金として認められないことがあります。
寄付金の種類や損金算入限度額、経済的利益の無償供与といった論点を理解し、適切に処理しましょう。
対価性・事業関連性・文書による裏付けを意識した処理を行い、税務調査へ備えることも重要です。