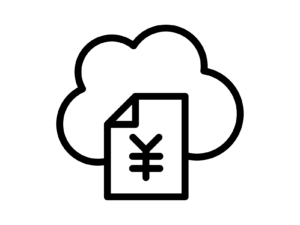土地の売却がある会社は要注意!『控除対象外消費税』の基本と経理処理

消費税の納税額の計算は年々複雑になっていますが、その経理方法にも注意が必要です。
特に気をつけたいもののひとつに「控除対象外消費税」があります。
これは仕入れや経費で支払った消費税の一部が、国に納める消費税から差し引けない(控除できない)ときに発生する消費税のことです。
「え、払った分は全部引けるんじゃないの?」と思うかもしれませんが、土地の売却や不動産収入など非課税の売上が多い会社などは、この控除対象外消費税が発生することがあります。
今回は、この見逃しがちな控除対象外消費税について、分かりやすく解説します。
目次
そもそも「控除対象外消費税」って
消費税の計算は、「売上と一緒にもらった消費税(預かり消費税)」から「仕入れや経費で支払った消費税(仮払い消費税)」を差し引いて、残りを国に納める、という仕組みが基本です。
この「差し引くこと」を「仕入税額控除」と呼びます。
では、なぜ「控除対象外」という差し引けない消費税が出てくるのでしょうか?
主な原因は、非課税売上という消費税を政策的にかけない収入があることです。
例えば、土地の売却や、住居用の家賃収入などは、消費税がかからない代表的な非課税売上です。
この非課税とされる収入を得るために使った経費や、購入した固定資産(建物など)にかかる消費税は、国としては「消費税をもらっていない売上」に対応するものだから控除させませんよ、というルールになっているのです。
会社全体の売上の中で、この「消費税がかかる売上(課税売上)」がどれくらいの割合を占めているかを計算するのが「課税売上割合」です。
この割合が低いほど、控除できない消費税、つまり控除対象外消費税の額が増えてしまうのです。
不動産業や医療・福祉などを営んでいる会社は課税売上割合が低くなる傾向があります。
控除対象外消費税の種類を区分しよう
控除対象外消費税はその発生原因が「何に使ったお金か」によって処理方法が変わります。
控除対象外消費税は、大きく分けて二種類あります。
- 「経費」や「棚卸資産(商品など)」にかかるもの
- 例: 事務所の電気代、事務用品代、仕入れた商品など
- 「固定資産」にかかるもの(資産に係る控除対象外消費税)
- 例: 会社が購入した建物、機械、車両など
このうち、1.の経費や棚卸資産にかかる控除対象外消費税については、実はそれほど心配いりません。
通常、雑損失や租税公課などその年の「損金(費用)」として全額処理することができます。
ただし、例外として接待交際費にかかる消費税については、法人税の計算で少し複雑なルールがあるので注意が必要です。
問題は2.の固定資産にかかる控除対象外消費税です。
この金額が大きいと、経費や棚卸資産とは異なった処理を行う必要が出てきます。
課税売上割合が80%未満の処理
会社の課税売上割合が80%未満で、なおかつ、一つの固定資産の取得にかかる控除対象外消費税が20万円以上になった場合は1回で経費処理ができません。
この場合の控除対象外消費税額は、その年の経費(費用)にはできず、「繰延消費税額等」という名前で、いったん会社の資産として計上しなければならなくなります。
資産に計上した繰延消費税額等は5年間かけて少しずつ経費にしていきます。
さらに資産を取得した最初の年だけは、5年間のうちの1年分ではなく、半分の金額しか経費にできません。
一括で経費にできる特例
固定資産にかかる控除対象外消費税は、原則として5年間で少しずつ費用にする「繰延処理」が必要になる場合がありますが、これには前述のとおり要件があります。
裏を返せば以下の3つの要件のどれか一つを満たせば、金額の大小にかかわらず、発生した年に全額を費用(損金)として処理することができます。
- その年の課税売上割合が80%以上だった場合
- その消費税が棚卸資産(商品や製品)にかかるものだった場合
- 一つの固定資産にかかる控除対象外消費税額が20万円未満だった場合
多くの会社は課税売上割合が80%未満となることはあまりありませんが、土地の売却などで一時的に非課税売上が大きくなったときは注意が必要です。
仮に課税売上割合が80%未満となった場合でも、一つの固定資産にかかる控除対象外消費税が20万円未満であれば、繰延計算をせずに一括で費用にできるので、経理処理がとても楽になります。!
税込経理なら気にしなくていいの?経理方式による違い
会社の消費税の経理処理方法には、大きく分けて「税抜経理」と「税込経理」の2つがあります。
- 税抜経理:消費税を本体価格と分けて記帳する方法。(例: パソコン本体10万円 + 仮払消費税1万円)
- 税込経理:消費税を本体価格に含めて記帳する方法。(例: パソコン11万円)
結論から言うと、税込経理を採用している会社は、基本的に控除対象外消費税額等について特別な処理をする必要はありません。
なぜなら、支払った消費税は最初からすべて、その資産の取得価額や経費の金額に含めて記帳されているからです。
この点だけ見ると、「税込経理の方が楽でいいな」と感じるかもしれません。
しかし、税込経理の場合、高額な固定資産の取得価額が消費税込みの金額で計算されるため、減価償却費(経費にできる金額)の計算や、中小企業向けの「少額減価償却資産の特例(30万円未満の特例)」などの判定基準にも影響を与えます。
どちらの経理方式を選ぶかは、会社の業種や規模によってメリット・デメリットがあります。
一度決めた方式は簡単には変えられないので、専門家である税理士などに相談し、自社に合った方法を選びましょう。
まとめ
控除対象外消費税は、特に不動産収入など非課税売上が大きい会社にとって、会社の利益計算に直結する見過ごせない問題です。
しかし、固定資産に係る控除対象外消費税がどうか、課税売上割合が80%未満かどうか、控除対象外消費税が20万円未満か、税抜経理方式を採用しているかなど資産計上しなければならない要件は多岐にわたります。
ご自身の会社の状況が不安な方は、お気軽にお問い合わせください。