消費税の会計処理で差がつく!法人の税抜・税込経理による有利不利

会社が日々行う経理処理。
その中で意外と見落とされがちなポイントが「税抜経理」と「税込経理」のどちらを採用するかという問題です。
これらは単なる表示方法の違いと思われがちですが、実は税務上の処理や節税の観点において大きな影響を及ぼすことがあります。
今回は税抜経理と税込経理の基本的な違いと、それぞれのメリット・デメリット、税務上有利なのはどちらなのかを解説します。
各経理方式の概要と基本的な違い
消費税の会計処理方法には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあります。
税込経理は、売上や仕入の際の消費税を本体価格に含めて記帳し、期末の決算時に税込表示する方法です。
消費税を分けて記載する必要はなく、まとめて処理すればよいため、特に会計ソフトを使っていない中小企業や個人事業主にとっては魅力的です。
消費税の納付時には租税公課として経費処理し、還付の場合には雑収入として収益処理を行います。
一方、税抜経理方式は、取引ごとに消費税を区別して記帳する方式です。
売上等の収入から区分した消費税を仮受消費税等勘定で処理し、仕入高等の支払金額から区分した消費税を仮払消費税等勘定で処理します。
収入や経費から切り離して処理されるため、期中でも正確な損益状況を認識できるというメリットがあります。
また、期末には仮受消費税と仮払消費税を相殺し、「未払消費税」または「未収消費税」として処理します。
どちらの方式を選択するかは企業の状況によって異なりますが、経営判断や税務戦略を考える上で重要なポイントとなります。
この経理方式の選択は消費税の課税事業者(納税義務がある者)が行うこととなり、消費税の免税事業者は税込経理のみとなります。
法人税への影響
次に、具体的な税務上の影響を見ていきましょう。
交際費
冗費などを節減する目的で交際費の取り扱いは、法人税法上経費にできる金額に制限が設けられており、資本金1億円以下の中小企業(大企業の子会社等一定の中小企業を除く)では、年間800万円までを上限として認められています。
この800万円という金額は税込経理と税抜経理の選択によって変わりはないため、経理方式の選択により納税額に影響を与えるケースがでてきます。
例えば、税抜で740万円程度の交際費を使うと、消費税も含めると800万円に達してしまい、その超えた部分の金額は法人税計算上の経費にならないため税込経理を選択した場合に納税額が増えることになります。
また、1人当たり5,000円以下の飲食費が交際費から除かれる規定に関しても同様の問題が生じます。
得意先などの接待のために支出した飲食費は基本的に交際費となり、上記の交際費課税の対象となります。
しかし参加したメンバー一人当たりの飲食費が5000円以下の場合、交際費として処理しなくとも認められる特例がありますが、この5000円の判定も税抜経理、税込経理で金額は変わりません。
そのため税込経理では5000円以下とならない飲食費が多くなり、結果的に上記の交際費課税が行われる可能性が高くなります。
交際費を積極的に活用する戦略的な営業を持つ企業や、接待・会食が多い業種の場合は、税抜経理を選択した方が有利となることが考えられます。
減価償却資産の処理
減価償却資産の取得に関しても、税込・税抜の選択は重要な影響を考えます。
法人税法上、取得価額10万円未満の資産は即時償却として購入年度の損金に算入でき、10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として3年均等償還、また、青色申告を行う中小企業においては30万円未満の資産を少額減価償却資産として購入年度に即経費化できる特例があります。
この場合の取得価額の判定は会社の会計処理方式によるとされており、税込経理方式を採用している場合は取得価額が税込価格で評価されるため、税抜経理方式と比べて取得価額が大きくなります。
税込10万2千円(税抜92,727円)の資産の場合、税抜経理なら10万円未満となり、即時経費化が可能です。
ただし、税込経理の場合は10万円以上となるため、3年均等償還となり、初年度の損金算入額が減少します。
また、少額減価償却資産の特例適用においても同様の問題が生じます。
税抜価格で28万円程度の資産は、税抜経理なら30万円未満となりギリギリ経費処理が可能ですが、税込経理では30万円を超えてしまい、通常の減価償却処理が必要になります。
このように、減価償却資産の判定においては、基本的に税抜経理方式のほうが税務上有利となります。
特に設備投資の多い企業や、小規模な資産を頻繁に購入する業種にとっては、この違いが企業の税金計算に大きな影響を与えるため、慎重に経理方式を選択すべきでしょう。
特別償却・特別控除
特別償却や特別控除の特例は、一定の要件を満たした場合に通常の減価償却より割増して償却できる制度や、法人税から一定額を控除できる制度です。
これらの制度の適用判定や控除額の計算においても、取得価額が重要な要素となります。
機械を取得した場合は取得価額が160万円以上かどうかでこの特例の適用可否が判定され、法人税の特別控除額も取得価額が計算の基礎になるため、税込経理方式が有利となります。
中小企業が積極的に設備投資を行う場合や、研究開発促進などの特別控除を活用する企業にとっては、税込経理方式を選択することでより大きな利益を得られる可能性があります。
事務処理の負担と経営判断
税込経理と税抜経理の選択では、税務上の有利不利だけでなく、事務処理の負担や経営判断の観点も重要な考慮要素となります。
税込経理方式の最大のメリットは、処理が簡単なことです。
各取引の経理処理時に消費税を分ける必要がないため、会計ソフトを使っていない小規模事業者にとっては事務負担の軽減につながります。
デメリットとしては消費税率の変更時にその影響を受けやすい点が挙げられます。
消費税率が変更されると、実際の売上高や経費の金額はさほど変わりはないのに去年と今年で業績が変わったように見えてしまいます。
一方、税抜経理方式のメリットは、期中の正確な利益把握が可能になることです。
税込経理方式では期末の消費税確定まで正確な損益がわからず、「売上が好調に見えても期末に消費税を入れたら案外利益は大きくなかった」という事態が起きます。
特に利益率の低いビジネスでは、この違いが経営判断に大きく影響する可能性があります。
一方、控除対象外消費税等の経理処理が煩雑になるというデメリットもあります。
居住用賃貸建物に係る消費税など消費税の計算上控除できない資産に係る消費税については約5年間にわたり経費処理する規定があり、そのための申告書を別途作成しなくてはならないなどの事務作業の負担が増加します。
しかし建物の償却期間が数十年と長いのに対し、5年で償却できるのはメリットにもなり得ます。
また、日々の会計処理において現代の会計ソフトの発達により、税抜経理方式の事務負担は以前より軽減されています。
多くの会計ソフトでは消費税の自動計算機能があり、入力の手間はさほど変わらない場合も多いです。
以上のように、事務処理の負担と経営判断の観点からは、企業規模や業種、利用している会計システムなどを総合的に検討して選択すべきでしょう。
まとめ
税抜経理と税込経理の選択は、企業の税務戦略的に重要な意思決定です。
交際費や減価償却資産の判定においては税抜経理が有利であり、特別償却・特別控除の適用では税込経理が有利となります。
企業の規模や業種、投資計画、会計システムの状況などを総合的に判断し、自社にとって最適な財務方式を選択することが重要です。
筒井会計事務所ではどちらの経理方式を選択した方が自社にとって有利となるかなどのご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

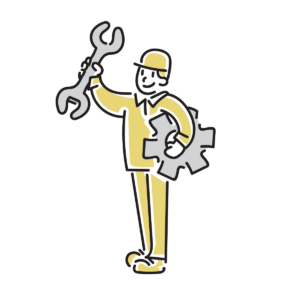

“消費税の会計処理で差がつく!法人の税抜・税込経理による有利不利” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。