固定資産は一時に経費にできない?減価償却の基本

「減価償却」と聞くと会計専門用語で難しいイメージを抱く方も少なくありません。
ですが、事業を行う上で避けては通れないのがこの減価償却です。
単なる会計処理にとどまらず、納税額にも大きく影響する項目ですので、減価償却の基本など概要をわかりやすく解説します。
減価償却とは何か
減価償却とは、資産の購入費用を一度に経費化するのではなく、耐用年数に応じて分割して経費にしていく仕組みです。
たとえば、100万円の機械を買った場合、耐用年数が10年なら100万円を10年間で経費化する、という考え方です。
これは「資産の価値が時間とともに減っていく」という経済的実態を反映するものでもあり、同時に「経費を複数年に分散させる」という会計処理でもあります。
減価償却の対象となる資産
減価償却の対象となるのは、固定資産のうち時の経過や使用によって価値が減少するものです。
代表的なものは建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、工具器具備品などです。
一方で、土地は減価償却の対象外です。
なぜなら、土地は時間が経っても原則として価値が減少しないと考えられているからです。
また、美術品や骨董品などのうち一定のものも、通常は価値が減らない資産として対象外となります。
また、取得価額によって取り扱いが異なる点にも注意が必要です。
例えば、取得価額が10万円未満の資産は一括で経費化可能、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却(いわゆる一括償却資産)、30万円未満であれば青色申告をおこなっている中小企業者等は「少額減価償却資産の特例」で即時償却可能です。
減価償却の方法
税務上の減価償却には大きく分けて定額法と定率法があります。
- 定額法:毎年均等額を経費に計上する方法。安定的に価値を発揮する建物などに適しています。
- 定率法:帳簿価額に一定割合をかけて償却する方法。初年度に多く償却でき、償却期間が経過するほど償却額は逓減します。
ここで押さえるべきは「法定償却方法」です。
法定償却方法とは事業者が税務署に減価償却の方法を届け出なかった場合に用いる減価償却方法で、法人の場合と個人の場合で異なります。
- 法人は定率法が原則(建物・建物付属設備・構築物・無形固定資産は定額法)
- 個人事業主は定額法が原則
届出書(減価償却資産の償却方法の届出書)を提出することで、個人・法人どちらも定額法・定率法を選択できます。
届出を行わなければ、法人は定率法、個人は定額法が自動的に適用されます。
さらに、例外的に建物・建物附属設備・構築物は定額法が強制です。
- 建物:1998年(平成10年)4月1日以降取得分から定額法のみ
- 建物附属設備・構築物:2016年(平成28年)4月1日以降取得分から定額法のみ
また平成19年3月31日以前取得の減価償却資産については現在の定額法・定率法とは計算方法や償却率の異なった旧定額法・旧定率法での計算が求められますので注意が必要です。
減価償却とキャッシュフローの関係
減価償却は会計上の経費ですが、実際のお金の流れと必ずしも一致しません。
この「ズレ」が経営者にとって大事なポイントです。
例えば、ある年度に100万円の機械を購入したとします。
実際のキャッシュフローは購入時点で一気に100万円が出ていきますが、会計上は耐用年数が10年なら毎年10万円ずつ経費として計上されます。
つまり、お金の支出は初年度に集中するのに、経費としての効果は複数年に分散して現れるのです。
この結果、年度ごとの利益とキャッシュフローの動きにズレが生じます。
購入初年度は「現金は大きく減っているのに、経費計上は一部だけ」、翌年度以降は「現金の流出はないのに、経費として計上が続く」という状況が起こります。
ただし、資産を使い切るまでの通算で見れば、支出した金額と経費計上額は同額です。
つまり長期的に見れば一致する仕組みなのです。
この「年度ごとのズレ」を理解しておけば、利益と現金残高が異なる理由がわかり、資金繰りの計画にも役立ちます。
法人と個人の違い ― 会計上の定期償却と税務上の任意・強制償却
法人と個人では、法定償却方法のほかにも減価償却の扱いに大きな違いがあります。
まず法人の場合、会計上は定期償却が原則です。
毎年計画的に償却しなければ決算書の信頼性が損なわれるため、ここは避けられません。
ただし、税務上は任意償却を許容しており、法人税の計算においては「償却するかどうか」は企業に委ねられていると言えるでしょう。
もっとも、計上しなかった分を翌年に繰り越すことはできないため、安易に判断すると不利になる場合もあります。
一方、個人事業主は強制償却です。
税務上も必ず法定の償却額を計上しなければならず、「今年はやめておこう」という選択肢はありません。
まとめ
減価償却は難解な専門用語に見えますが、その内容は費用の期間配分です。
今回は概要の説明のため各論点には触れませんでしたが、取得価額や耐用年数、残存簿価など検討しなければならない項目は多岐にわたります。
税理士でも勘違いしやすい内容もありますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


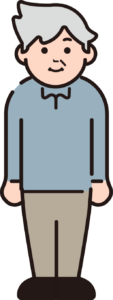
“固定資産は一時に経費にできない?減価償却の基本” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。