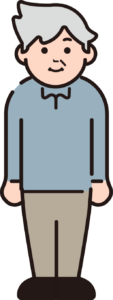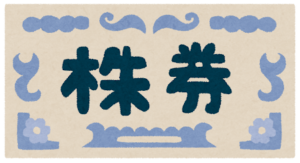個人事業主にも退職金を!小規模企業共済で老後の不安をなくそう

「会社員みたいに退職金がないから老後が不安…」そんな風に考えている個人事業主の方は多いのではないでしょうか。
国の制度である小規模企業共済は、そんな個人事業主の不安を解消してくれる心強い味方です。
この制度は、税金を減らしながら、将来に向けた資金を積み立てることができる、まさに一石二鳥の仕組み。
今回は、この小規模企業共済がどんな制度なのか、どんなメリットがあるのか、そして注意すべき点まで解説します。
目次
小規模企業共済の概要
小規模企業共済は、国が運営する個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。
加入できるのは、個人事業主や小規模法人の役員などで、毎月1,000円から70,000円まで、500円単位で自由に掛金を設定できます。
途中で掛金の額を変えたり、一時的に支払いを止めたり、年払いにしたりすることも可能です。
さらに嬉しいポイントは、払い込んだ掛金の全額が「所得控除」になることです。
つまり、確定申告でこの掛金分を差し引くことができるので、その年の税金(所得税・住民税)を減らすことができるのです。
万が一、事業をやめたり、役員を退任したり、老齢給付の条件を満たした場合などに、積み立てたお金を「退職金」や「年金」のように受け取ることができます。
病気や災害などで急にお金が必要になったときには、積み立てた金額の一定の範囲内で、低い金利で借り入れができる契約者貸付制度も利用できます。
節税効果
小規模企業共済の最大の魅力は、やはり「節税効果」です。
では、具体的にどれくらいの効果があるのでしょうか?
税金は、収入から経費や所得控除を差し引いて計算される課税所得に対してかかります。
小規模企業共済の掛金は、この所得控除に当てはまるので、掛金が増えるほど課税所得が減り、結果として税金が安くなるという仕組みです。
例えば毎月3万円(年間36万円)の掛金を支払っている方の所得税と住民税を合わせた税率が30%だとすると約10.8万円の節税効果が期待できます。(36万円 × 30%)
共済金の受給時には課税されますが、その受け取り方法によって税金の計算方法が大きく変わるので、出口戦略がとても大切です。
「一括」で受け取る場合
この一時金は原則として退職所得として扱われます。
退職所得には退職所得控除という大きな優遇措置があり、税金がほとんどかからないケースも多いです。
長年積み立てていればいるほど控除額が大きくなるので、税負担をかなり抑えられます。
しかし、他の退職金やiDeCoなどを受け取るタイミングと重なる場合は、退職所得控除が減ってしまうことがあるので注意が必要です。
2025年度の税制改正により、iDeCoの老齢一時金を受け取った年の後9年間に他の退職手当などを受け取ると、退職所得控除の計算方法が変わるようになりました。
iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業年金など、他の退職金制度を利用している場合、小規模企業共済と受け取りのタイミングが重なると、税金の計算で不利になることがありますので、受け取る時期を計画的にずらしたり下記の分割での受給も検討しましょう。
「分割」で受け取る場合
各年に受け取った金額は公的年金等の雑所得として扱われます。
こちらは年金のように少しずつ受け取るので、その都度税金がかかります。
この時、受け取った金額にそのまま課税されるのではなく、公的年金等控除という控除額を差し引いた後の残額に対して課税されます。
まとまったお金ではなく、収入を平準化したい場合に有効な方法です。
どちらの方法にもメリット・デメリットがあるので、受け取るタイミングで、その年の他の所得や税金も考慮して最適な方法を選ぶようにしましょう。
小規模企業共済の注意点
小規模企業共済は素晴らしい制度ですが、いくつか注意すべき点もあります。
短期解約
この制度は、長く続けることでメリットが大きくなる仕組みです。
そのため、加入から20年未満で任意解約してしまうと、払い込んだ掛金の合計額よりも少ない金額しか戻ってきません。
これは短期間で掛け金を減額した際も同様です。
事業の資金繰りが厳しくなったからといって、安易に解約すると大きな損をしてしまいます。
資金が固定される
毎月の掛金を支払いますので事業に必要な現金はその分減少します。
特に、創業間もないタイミングなどでは本来事業に必要なキャッシュが足りなくなり、資金繰りを圧迫してしまうことがあります。
契約者貸し付けも借入の一種
困ったときに利用できる契約者貸付は心強い制度ですが、借りたお金には1.5%の利息がかかります。
安易に借り入れを繰り返すと、返済負担が重くなり、かえって資金繰りが悪化する原因になりかねません。
国民健康保険の削減効果はない
国民健康保険料の計算の基礎は、小規模企業共済の掛け金を控除する前の合計所得金額となります。
そのため小規模企業共済の支払の有無は国民健康保険料に影響を与えません。
まとめ
小規模企業共済は、節税と将来の資金準備を同時に実現できる、個人事業主にとって非常に魅力的な制度です。
しかし、そのメリットを最大限に活かすためには、無理のない掛金設定と、長期的な視点が何よりも重要です。
毎月の資金繰りをしっかり確認し、無理のない金額から始め、将来のライフプランや事業計画と合わせて、賢く活用していきましょう。
もし、ご自身の状況に合った最適なプランが分からない場合はお気軽にお問い合わせください。