知っておきたい!自己株式の会計・税務のポイント
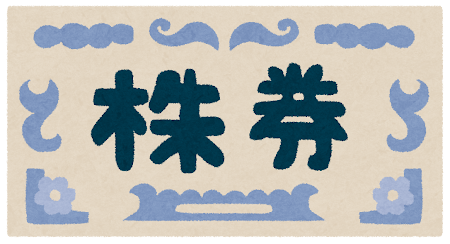
上場企業では株価対策や株主還元策を目的として自己株式の取得がニュースで聞かれることが多くなってきました。
株主から自社株式を買い取るという一見シンプルな取引ですが、その裏では会社法上の決まりや、会計・税務上の複雑なルールがありますので注意しなければなりません。
今回は、非上場会社が自己株式を取得した際の基本から会計・税務のポイントを解説します。
自己株式とは
自己株式とは、会社が自社の株主から買い戻した自ら発行した株式を指し、金庫株と呼ばれることもあります。
非上場企業では事業承継時の納税資金の確保や株主構成の調整といった目的で行われることが多いです。
自己株式の大きな特徴は、取得した株式は議決権や配当請求権といった「株主権」を失う点です。
また、取得した株式を消却すれば発行済株式数が減少し、残存株主の持株比率が相対的に上昇する効果もあります。
ただし、会社が自由に株式を買い戻せるわけではなく、会社法上の制約がありますし、今後は種類株式の権利行使により取得するケースが増える可能性もあります。
会社法における自己株式の取扱い
会社法では、自己株式の取得は原則として株主総会の決議が必要とされています。
特定の株主より自己株式を買い取る場合は特別決議(株主の過半数の出席、出席した株主の2/3以上の賛成)が求められます。
取得原資については、債権者保護の観点から一般的に分配可能額の範囲内で行わなければなりません。
この分配可能額は、基本的に剰余金等の額の合計額から自己株式の帳簿価額等を控除して算定され、自己株式取得時までの異動も加味されます。
取得した自己株式はそのまま保有することも可能ですが、自由に処分・消却することができます。
会計上の処理と表示
会計上、自己株式は資産ではなく純資産の控除項目として処理されます。
取得した株式の取得価額は貸借対照表の「純資産の部」から差し引かれて表示され、自己株式を取得した際の取得に要した手数料や付随費用は営業外費用として経費処理します。
また、自己株式の取得・消却・再発行のいずれにおいても、損益計算書には原則影響を与えません。
つまり、自己株式の取得等によって「儲かった」「損した」といった損益は発生しないのです。
自己株式の処分時には、処分価額と帳簿価額の差額は資本剰余金で調整し、損益には計上しません。
自己株式を無償で譲り受けた場合も受贈益のような会計処理は発生せず、自己株式の数だけ増加させます。
税務上の取扱い
法人税法上、自己株式の取得は原則として資本取引とされ、会社の損益に影響を与えません。
ただし、交付金銭等の額と資本金等の額のうち当該株式に対応する部分との差額については、「みなし配当」として処理され、利益積立金額を減少させることになります。
具体的には、みなし配当の額は以下の算式で計算されます。
みなし配当の額 = 交付金銭等の額 - 資本金等の額 × 取得株式数 ÷ 発行済株式総数
税務上はみなし配当も配当の一種なので源泉徴収が必要になります。
非上場会社が自己株式を取得する際はこのみなし配当の額の20.42%を源泉徴収し、支払月の翌月10日までに納税を行います。
また株主には『配当等のみなす金額に関する支払調書(支払通知書)』を交付し、税務署にも支払調書を支払調書合計表とともに、支払からひと月以内に提出します。
なお上場会社が市場から自己株式を取得する場合はこのみなし配当課税の対象から除外されます。
まとめ
自己株式は、会社法上も押さえなければならないルールがあり、会計・税務上も重要な論点がある取引です。
取得側で間違えた処理をすると、売却側にも影響を及ぼしますので慎重に判断することが求められます。
自己株式の取得を検討される際に不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


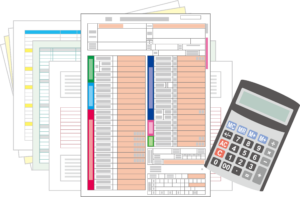
“知っておきたい!自己株式の会計・税務のポイント” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。