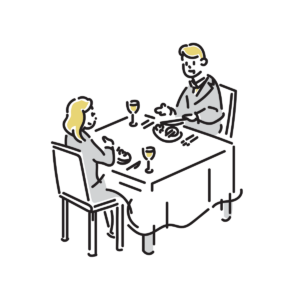意外と知らない落とし穴も~合同会社の事前確定届出給与~
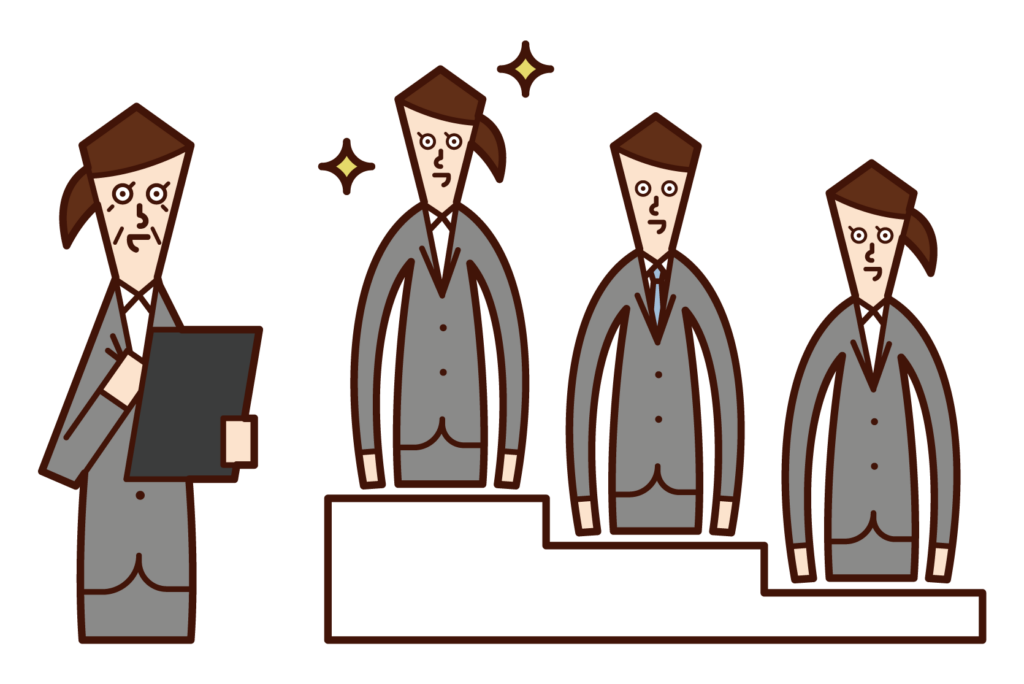
最近、設立が手軽で費用も抑えられることから、合同会社を設立する方が増えているようです。
しかし、手軽さの裏には、税務上の意外な落とし穴が潜んでいることも事実です。
特に、役員に賞与(ボーナス)を支払う際のルールをきちんと理解しておかないと、後で「経費にできない!」という事態になりかねません。
今回は、国税庁の質疑応答事例より、合同会社の役員賞与に関する重要なポイントを、分かりやすく解説していきます。
事前確定届出給与とは
事前確定届出給与とは、決められた時期に確定した金額を役員(取締役や監査役など)に支給する旨を定め、事前に税務署へ届出を行うことで、役員賞与などが損金算入できる制度です。
賞与を含めた役員報酬は一定のものしか損金(法人税法上の経費)に算入できません。
事前確定届出給与として役員賞与を損金算入するためには、期限内の届出が絶対条件です。
届出の期限は、「株主総会等の決議日(合同会社の場合は定時社員総会の開催日)から1ヵ月以内」、または「事業年度開始日から4ヵ月以内」のいずれか早い日です。
届出を1日でも過ぎてしまえば、たとえ金額が合致していても、その役員賞与は全額損金不算入となります。
合同会社の場合、定款で定時社員総会を定めていても、その開催日が遅れてしまうと、自動的に「事業年度開始日から4ヵ月以内」が期限になってしまい、届出が間に合わなくなるリスクがあります。
定款に報酬の定め
合同会社は、所有と経営が一体化した組合的な会社とされています。
そのため、原則として社員(出資者)全員が業務執行権限を持っていますが、定款で特定の社員を「業務執行社員」として定めることも可能です。
報酬の金額や支給方法は、原則として「定款で定める」か「社員全員の同意もしくは社員の過半数の決議で決定」します。
定款に具体的な金額を記載する方法もありますが、変更の都度定款変更が必要になるため、報酬決定方法のみを記載し、具体的な金額は総社員の過半数の同意などで毎期決定するケースが一般的です。
業務執行役員への賞与も社員の過半数の決議などが必要になってきます。
社員総会
合同会社には、法律で定められた機関として「社員総会」は存在しません。
これは、株式会社の「株主総会」に当たる会議体ですが、合同会社では法定されていないのです。
しかし、今回取り上げている文書回答事例では、「定時社員総会」の開催が前提となっています。
なぜ社員総会が重要になるのでしょうか?
それは、役員賞与を「事前確定届出給与」として損金算入するために必要な手続きと関係してきます。
事前確定届出給与とは、いつ、誰に、いくらボーナスを支払うかを事前に税務署に届け出て、その通りに支給することで、経費として認められる制度です。
事前確定届出給与に関する届出書には提出期限が設けられており、役員給与の額を決める「株主総会、社員総会その他これらに準ずるもの」の決議日または職務執行開始日から1ヵ月以内に届出を出す必要があります。
文書回答事例では、定款で定めた定時社員総会が「株主総会等に準ずるもの」と見なされています。
もし定款に社員総会の定めがなければ、この手続き自体が難しくなってしまうかもしれませんので、合同会社で事前確定届出給与を適用するには、定款で社員総会を定めていることが前提となる可能性があるのです。
業務執行社員の任期
事前確定届出給与の届出期限の一つに、「職務の執行の開始の日」から1ヵ月以内というものがあります。
この「職務の執行の開始の日」をどう判断するかが、合同会社では難しい問題になります。
合同会社の業務執行社員の任期については法的な定めはありません。
そのため社員となった日の属する事業年後以後については、職務の執行が開始された日が明らかではないこととなります。
今回の事例では、定款で業務執行社員の任期を10年と定めており, 定時社員総会の開催日を「職務の執行の開始の日」としていました。
これにより、届出期限を定時社員総会から1ヵ月後と判断できたわけです。
まとめ
合同会社の役員賞与は、一見シンプルに思えて、実は税務上の注意点がたくさんあります。
特に、以下のポイントは絶対に押さえておきましょう。
- 定款に「業務執行社員への報酬支給」の定めがあるか。
- 定款に「社員総会」や「業務執行社員の任期」が明記されているか。
- 事前確定届出給与の届出は期限内に提出できているか。
ご自身の会社の定款は大丈夫か、この機会にぜひ確認してみてください。