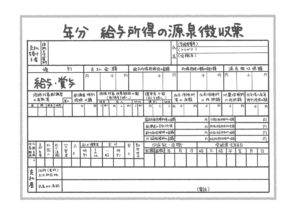税務調査の常識が変わる!オンライン化で経営者が知っておくべきこと

皆さんは「税務調査」と聞いて、どんなイメージをお持ちでしょうか?
突然の連絡、分厚い資料の準備、そして税務署の方との長時間にわたる対面でのやり取り…といった、ちょっと憂鬱なイメージをお持ちの方も少なくないかもしれません。
しかし時代は大きく変わりつつあります。
国税庁が「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)」を推進しており、いよいよ税務調査にもオンラインツールの活用が本格的に導入される見込みとなりました。
今回は、この税務調査のDX化について、分かりやすく解説していきます。
目次
税務行政のDXって何?中小企業にとってのメリットは?
国税庁は今、納税者の皆さんの利便性を向上させるとともに、税務行政の効率化を図るために、税務行政全体のデジタル化を進めています。
これが「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)」と呼ばれるものです。
具体的には、デジタル技術を積極的に活用して、国税に関する手続きや業務のあり方を根本的に見直そうという取り組みです。
令和7事務年度(令和7年9月)からは、税務調査などもオンラインツールを使って行われるようになる予定です。
大規模法人では、すでに令和5年7月からオンラインでの調査が試行的に実施されています。
私もこの税務行政のDX化によって、行政側のコストが圧縮され、それが結果的に私たちの税金がより効率的に使われることに繋がれば、とても素晴らしいことだと感じています。
さらにオンライン化によって税務調査の期間が短縮されたり、準備の手間が軽減されたりといった恩恵が受けられるものであってほしいと強く願っています。
もしそうなるのであれば、これは単なるデジタル化ではなく、私たち中小企業経営者にとって、まさに「良い変化」と言えるのではないでしょうか。
導入されるオンラインツール
令和7事務年度からは、税務調査や行政指導、あるいは書面添付制度に係る意見聴取(これらをまとめて「調査等」と呼びます)を行う際に、必要に応じてオンラインツールが利用されるようになります。
具体的にどんなツールが使われるかというと、以下の3つです。
- インターネットメール
これまで電話や書面で行われていた「調査等の事前通知後の連絡」などが、メールで届くようになります。
例えば、「調査の際に準備していただく資料の依頼」なんかがメールで来るイメージですね。 - Web会議システム(Microsoft Teams)
面談、つまり税務調査におけるヒアリング(質問・回答)などが、Teamsを使ってオンラインで行われるようになります。
面談の都度、わざわざ税務署や自社に来てもらう必要がなくなり、遠隔地からでも参加しやすくなります。 - オンラインストレージサービス(PrimeDrive)
帳簿書類などの電子データを税務署に提出する際に、インターネットメールやe-Taxの他に、PrimeDriveというオンラインストレージサービスを使ってデータのやり取りができるようになります。
大容量のデータもスムーズに送受信できるようになるので、紙の資料を準備する手間や郵送の手間が省けますね。
これらのオンラインツールを使うには、事前にMicrosoft Formsというシステムを使って、利用に関する同意事項などを登録する必要がありますので、ご留意ください。
オンラインツール利用までの流れ
新しいツールの導入と聞くと、少し身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、オンラインツール利用までの流れはとてもシンプルで分かりやすく設定されています。
- メール利用の意思確認:
まず、調査担当者から、オンラインツール(メール)の利用について確認があります。
納税者の皆さんの利便性向上や税務行政の効率化につながる場合に提案されます。 - 同意事項やメールアドレスの登録:
もし利用に同意するなら、Microsoft Formsというオンラインの入力フォームを使って、同意事項やメールアドレスなどを登録します。
このFormsは、デジタル庁が提供する政府共通の業務実施環境であるガバメントソリューションサービス(GSS)の一部として、国税庁職員が利用できるようになるツールの一つです。 - テストメールの送受信
登録が完了すると、調査担当者から登録したメールアドレスに「テストメール」が送信されます。 - 受信状況の確認
最後に、調査担当者から電話で、テストメールがきちんと届いているかどうかの確認が行われます。
このように、段階を踏んで丁寧に確認してくれるので、初めてオンラインツールを使う方でも安心して進められます。
事前にこの流れを知っておけば、いざという時にも慌てずに対応できるでしょう。
電子データの提供と情報保護
オンライン化が進むと、帳簿書類などの電子データを税務署に提供する機会が増えてきます。
提供したデータの情報保護がしっかり行われるのか非常に気になるところですが、国税庁はこの点についても配慮しています。
電子データの提供を受ける際には、提供された電子データが国税当局でどのように取り扱われるかを記載した文書を交付したり、その内容を口頭やメールで説明したりする取り組みを実施する予定です。
説明される主な内容は次のとおりです。
- 国税職員には、調査で取得した電子データについて「守秘義務」が課されており、もし漏洩させてしまった場合には罰則の対象になること。
- 国税庁では、情報セキュリティに関する規則を定め、職員は職務上必要な情報しか利用できないような仕組みを構築していること。
- 提供された電子データは、国税庁が定めた規則に基づいて厳重に管理され、保存期間が終われば確実に消去されること。
もちろん、私たち自身も、提供する電子データの管理には引き続き注意を払う必要があります。
中小企業経営者が今からできる準備と今後の展望
税務調査のDX化は、中小企業経営者にとってこれまでの税務調査の常識を覆すような変化です。
この変化をチャンスと捉え、前向きに対応していくことが大切です。
今からできる準備としては、まず自社のIT環境を見直すことが挙げられます。
インターネットメールやWeb会議システム、オンラインストレージサービスをスムーズに利用できる環境が整っているか確認しましょう。
またオンラインでのやり取りが増えることで、これまで以上に税理士との連携も重要になってきます。
税理士の先生方と密にコミュニケーションを取り、オンライン調査への対応についても相談しながら進めていきましょう。
新しい技術の導入は、時に戸惑いもあるかもしれませんが、この変化を乗りこなすことで、より効率的でスマートな税務調査対応が可能になるはずです。
繰り返しになりますが、私個人の意見としてはこのDX化によって納税者側にも調査期間の短縮や手間の軽減という形で具体的に還元されることを強く期待しています。
もし、調査に要する時間や、それに伴う私たちの業務の中断が大幅に短縮されるのであれば、これは経営にとって非常に大きなプラスになるはずです。
まとめ
税務調査のDX化は、もはや遠い未来の話ではありません。
令和7事務年度からは、オンラインツールを活用した税務調査が本格的にスタートします。
この変化は、行政の効率化だけでなく、私たち納税者にとっても調査期間の短縮や準備の簡素化といった恩恵をもたらす可能性を秘めています。
新しい時代に合わせた税務調査の形に、私たちもいち早く慣れて、スムーズな企業経営を目指していきましょう。