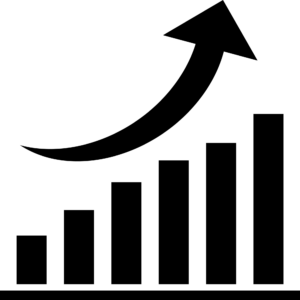年間100時間超えも! 税理士が「学び」を止められない、これだけの理由

「先生」と呼ばれる士業の一つ、税理士。
この資格の重みを感じながら日々業務にあたっています。
皆さんは税理士にどんなイメージをお持ちでしょうか?
私は税理士の仕事は単に税金を計算することではないと思っています。
お客様の未来を支え、社会に貢献するために、私たち税理士が心に刻むべき矜持(きょうじ)があります。
今回は、私が考える税理士としての哲学の中でも、特に学びへの姿勢と責任の重さに焦点を当てて語らせていただきます。
目次
学びの時間の確保は必須
税理士の仕事は、毎年のように目まぐるしく変わっていく法律や制度というルールを扱う専門職です。
ただでさえ膨大な法律や基準などの情報に加え、改正も追っていくためには常に学び続けることが重要だと思います。
そのため私たち税理士には、年間36時間以上の研修受講義務が課せられおり日本税理士連合会のホームページで各税理士の認定研修の受講時間が公表されています。
これは、お客様に最新かつ正確な情報を提供し続けるための、いわば最低ラインです。
しかし、この36時間だけでお客様の経営や財産を深くサポートし続けるのは、到底無理です。
税制改正はもちろん、事業承継やデジタル化への対応など、私たちがカバーすべき分野は膨大にあります。
そのため、真にお客様のために動こうと決めている税理士は、税理士会認定の研修以外にも、専門分野のセミナーや業界団体の研究会、独自の情報収集を含めると、年間100時間をゆうに超える学習時間を確保しているのではないでしょうか。
この「100時間の壁」を超える努力こそが、お客様の大切な財産や経営に関わる税理士の覚悟とも言えます。
完璧ではないと感じながら、120%を出し切るプロの誠意と責任
税理士の仕事は、広大で変化し続ける税の世界が相手です。
そのため、「自分の仕事が100%完璧だ」と言い切れるプロは存在しないでしょう。
なぜなら、どれだけ深く学んでも、知識には必ずまだ先があると知っているからです。
しかし、私たちはこの「100%の完璧な準備は難しい」という事実に甘えるわけにはいきません。
もし「完璧な準備ができないから」と、ふがいないサービスしか提供できないなどと言い訳をするなら、それはプロとしての責任放棄です。
プロの矜持とは、この不足を知りながらも、お客様と向き合うときには持てる知識と能力をすべて出し切り、自分のできる120%のパフォーマンスを見せることです。
「自分に今できる最高のサービスはこれです」と心から信じ、自信を持ってサービスを提供する。
この自信の裏には、裏腹に存在する「自分にはまだ足りない」という謙虚な不足感があります。
「自分への不足」と「プロとしての自信」という矛盾を常に持ちながら、ひたむきに自分の目指す税理士像に向かっていく。
この姿勢こそが、プロとしての誠意と責任感の現れであり、それを埋めるべく学び続けることこそが最も重要なことなのです。
税理士の責任は重い。だからこそ現場を従業員任せにはできない
私たち税理士は、お客様の税務申告という極めて重要な業務を代行します。
この税理士業務は、税理士法に定められた資格者にしかできないものであり、その資格の裏側には、お客様の財産と会社の未来、そして国家の税務行政に対する重い責任が伴います。
この責任の重さを考えれば、業務を従業員に丸投げしたり、任せっきりにするという税理士はいないでしょう。
もちろん、組織として分業や効率化は必要です。
しかし、お客様との重要な面談、最終的な経営判断に関するアドバイス、そして税務書類の最終確認など、責任の所在に関わる部分には、資格者である税理士自身が深く関与する必要があります。
万が一、申告ミスや重大な問題が発生した場合、最終責任を負うのは、その業務を受任した税理士です。
担当者に任せているから中身はわかりません、という言い訳は通用しません。
「資格者が責任を持つ」という大原則を貫くことが本当に重要だと思います。
脱税・粉飾はNGだが、他の方法を模索するためにも学びが必要
私たち税理士の仕事の根幹は、「公正な立場で申告納税制度の適正な実現に奉仕すること」です。
お客様から「とにかく税金を安くしてほしい」という要望があったとき、安易に脱税や粉飾といった違法行為に手を染めることは、税理士としての倫理に真っ向から反します。
不正な手段は、お客様に追徴課税という重いペナルティや信用の失墜をもたらし、未来を破壊しかねません。
では、不正を拒否するだけで十分でしょうか?
私たちは、単に不正をしないだけでなく、不正をしなくてもお客様の利益を守れる方法を検討する義務があります。
そのためには、法律や会計の深い知識はもちろん、企業の経営状況や業界特有の事情に合わせた合法的な節税策、税制優遇措置、事業再編のスキームなど、多角的な知恵を絞る必要があります。
この他の方法を模索し、見つけ出し、お客様に提示する能力こそが、税理士の真の価値です。
もちろん、どれほど検討しても明確な答えが出ないこともあります。
しかし、どれだけの研鑽を積んでその答えに至ったのかという過程こそが、その仕事に重みを与えるのです。
そして、その力の源こそ、絶え間ない学びによって培われると思います。
手数料目的の提案はNo! 真にお客様のためになる判断とは
私たち税理士は、お客様のリスクヘッジや節税対策の一環として、保険や様々な節税商品のアドバイスを行うことがあります。
しかし、ここで絶対に守らなければならない倫理があります。
それは、「お客様の利益」ではなく、「自らの紹介手数料」を目的とした提案は行わないということです。
長期的な視点に立ち、会社の財務体質強化やリスクヘッジに本当に役立つ生命保険や、経営計画に沿った合理的な節税策であれば、積極的に提案すべきです。
しかし、中には、短絡的な節税効果だけを謳い、実態として会社に重荷となる高額な保険や、過度な節税商品が存在します。
税理士がこれらの商品の紹介フィーを目当てに、お客様にメリットのない取引を強いるのは、専門家としての信頼を裏切る行為に他なりません。
そして何より、お客様自身も税理士の提案を鵜呑みにするのではなく、その取引が自社の経営にとって長期的に見て本当に利となるのかを最終的に判断する力を持つことが重要です。
お客様に本当に資する商品なのかどうかを判断するためにも、学びが必要になってきます。
まとめ
今回は、税理士として求められる学びへの姿勢などについて語らせていただきました。
税理士の方々は本当に勉強熱心な方が多く、私もそのような方々から日々刺激を受け、学ばせていただいています。
お客様の未来のために最高のサービスを提供できるよう、今後も私たち自身のアップデートを続けていく所存です。
経営に踏み込んだアドバイスなどが欲しいといった方は、まずはお気軽にお問い合わせフォームからご連絡をお待ちしております。